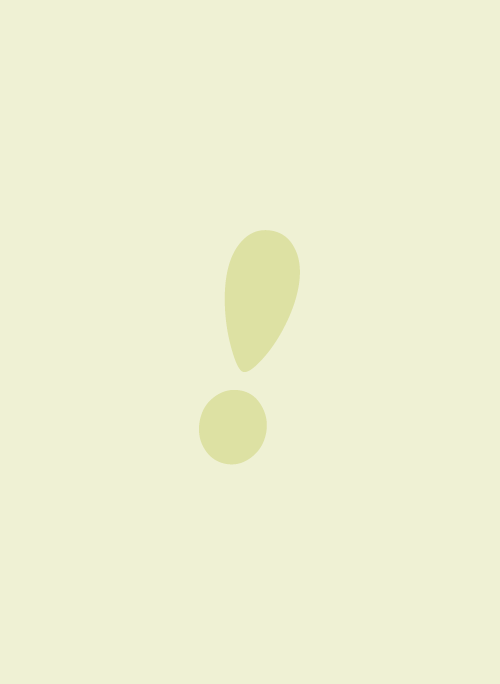「萱村の血に――俺に、復讐するとか言って。山吹と同じところへ萱村の人間を行かせないために、自分の子供使ってまで、半分化け物になってまで……なのに、こんなあっさり終われるのかよ」
「おまえだって、好いた女が死ぬかもしれないとなれば、あっさり復讐のことなど忘れたじゃない」
「それは……」
朔は言いよどみ、腕の中の銀花を見下ろす。
晦の魂は連れていかれ、白檀も自滅しようとしている。
父や一族の者たちを呪い殺した犬神は憎いが、所詮は白檀に使役されたにすぎない妖など、朔にとって復讐の対象にはなりえない。
復讐の機会は永遠に失われた。
それでも、今、銀花の肩から手を離して刀を取る気にはならない。
穏やかな顔で寝息を立てる銀花を愛しいと、離したくないと、思う。
自分でも笑ってしまうほど情けない。
十年追い続けた仇が目の前にいるのに、殺そうと思えないなんて。
「ひとの心など、ときに当人もわけがわからなくなるほど複雑なものよ」