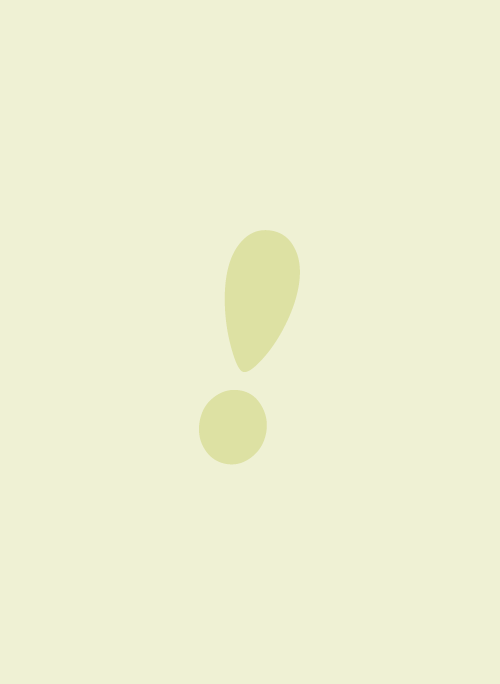その間にも、白檀の顔のひびはどんどん増えていく。
「あなたも退治屋の端くれなら、わかるでしょう? 妖を使役することは、己れの命を分け与えること。……わたくしの命は、もうほとんど残っていなかったのよ」
そして残り少ない命をすべて、銀花の傷を治すことに注いだために、限界が来た。
白檀も、玉響も、そうなることをわかっていたのだ。
ぽろ、と、白檀の指先が土塊のように崩れ落ちた。
魂を妖に食わせた者は、死した後、幽世には行けない。
当然だ。
幽世に行くべき魂がもう存在しないのだから。
そしておそらくは力を得るために大蛇を喰らい邪に転じた白檀は、もう人らしい死すら許されなかった。
崩れた指の断面から、さらさらと砂のように塵のように、白檀の体がこぼれ落ちる。
「……わからない」
ぽつりと、朔がつぶやいた。白檀は怪訝そうに眉をひそめる。