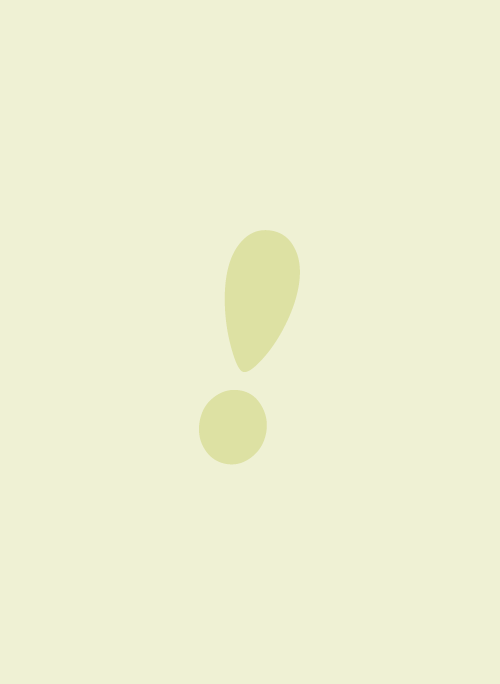そう言って、山吹はおんぶ紐をほどくと、背に背負っていた赤子を胸の前で抱きかかえる。
「泉の下にはね、水月鬼が妖力で作り出した水月鬼の棲家があるの。わたしや月詠は、しばらくそこに隠れておくわ。
けれど赤子の体には妖力がこたえるみたいで、この子をそこには連れていけない」
山吹の瞳が潤んだように見えた。
それもたった一瞬のこと、山吹はまぶたを伏せて、赤子の頬に口づけを落とす。
「だから、あなたに託すわ。あなたは、白檀の信頼する人だから」
なんでもないような笑顔で、お願い、と言った小さな声は震えていた。
きっと不安だった。きっと心配だった。
きっと、誰かに預けたりせず、自分でずっと抱いて逃げたかった。
しかも、それができた。
山吹と赤子の銀花だけなら、殺されはしないのだから。
――けど、命を狙われている月詠をほうっておくことが、このひとにはどうしてもできなかった。
山吹の考えていたことが、手に取るようにわかる。
三人で、生きたかった。
三人で、幸せになりたい。
三人じゃないと意味がない。
――きっと自分だってそうした、と、銀花は思った。