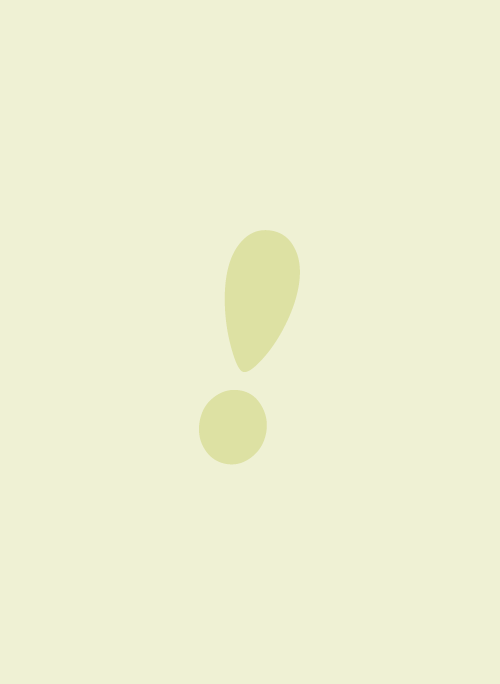一体何が、彼にそんな顔をさせるのか。
実の弟を、なぜ痛みをこらえながらも憎み続けるのか。
なぜ、憎い相手を憎むことに、彼がそんなにも傷つかなければならないのか。
「あたしも家族を知れば、わかるんじゃないかと思ったの」
だからね、萩。
と、銀花は柔らかな笑みを浮かべて、格子の隙間に右手を伸ばし、萩の白い左手を取った。
「心配してくれてありがとう。でも、あたし、父様や母様が恋しくて二人のことを知りたいわけじゃないわ。
あたしは、朔のことをわかりたいの。朔を追いかけるために、それが必要だから」
言ってから、自分の言葉に目が覚めるような心地がした。
昨日の晦の一件以来、無性に感じていた焦りの理由がわかった。
(そうだ。あたしは、朔を追いかけたいんだ)
朔が遠くなってしまった気がしていた。
朔が晦を追いかけて行ってしまえば、もう二度と帰ってきてはくれない気がしていた。
――だから、追いかけたくて。
けれど追いかけたところで、どんな言葉をかければいいのかがわからなくて。