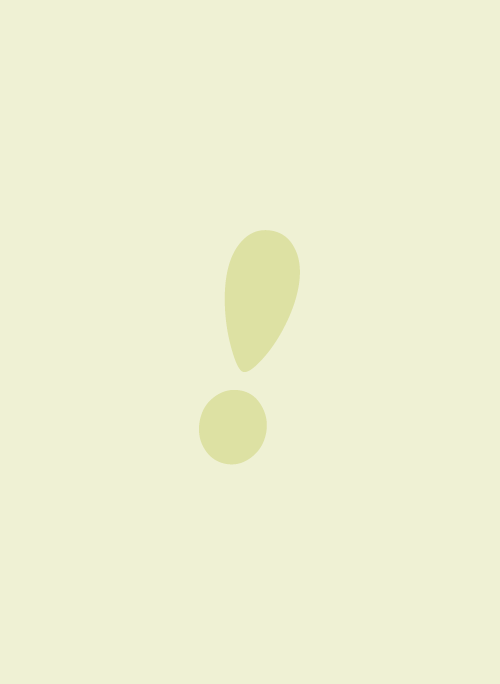「二藍を怒らないで、猫目」
何か言おうと猫目が唇を開いたとき、二藍へ向けられた猫目の視線を遮るように銀花は一歩前へ出た。
「あの、晦というひと。あのひと、二藍にいつの間にか幻術をかけていたの。だから二藍には短刀が見えなかった」
晦が銀花めがけて短刀を投げる一瞬前、二藍から異質な妖気を感じた。
人間には感じ取ることのできないほどかすかな、――半妖である銀花だからこそわかる、二藍のものとは微妙に違う妖気。
朔も猫目もまったく気がつかなかったのだろう。
本当か、と言う朔に銀花は頷くと、しゃがみこんで、うなだれた二藍の頭を撫でる。
「だから、そんなに落ち込まないで」
「…………ごめん、銀花。猫目に任されたのに……」
「無事だったんだから、いいの」
銀花が言うと、二藍はおそるおそる顔を上げ、上目遣いに猫目を見上げる。
なんだかんだ言って、やはり二藍も今様も、猫目の式なのだ。
普段は猫目を茶化してばかりいても、彼らの主人は猫目。
猫目の命令は絶対で、猫目に許されなければ銀花の慰めなど意味はない。