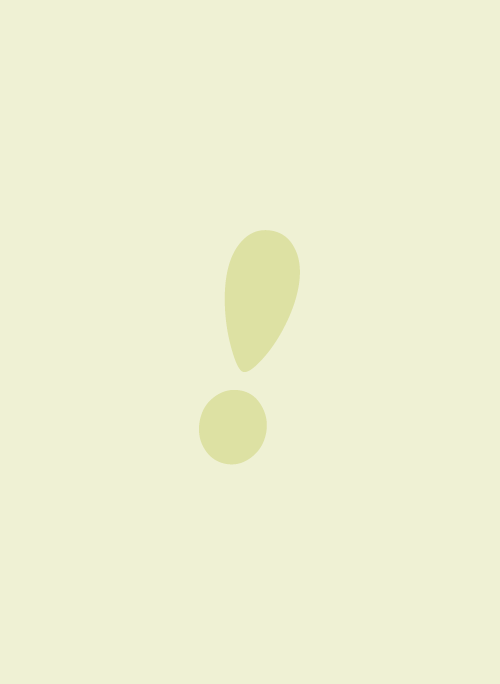銀花がつぶやいた、次の瞬間。
ザッ、と土を踏む音がして、銀花の隣に降り立つ影があった。
目のチカチカするような朱色の着物に身を包んだそのひとは、
顎の下で切りそろえた短い髪から男のように見えたが、柔らかく端正な顔立ちと線の細い体つきは女のようだった。
「やっと見つけたぞ、馬鹿弟子」
男にしては高く、女にしては低いその声は、誰に向かって放たれたものなのか。
それはすぐにわかった。
朔が、「師匠……」と呟いたからだ。
銀花は目を丸くして、隣に立ったそのひとをまじまじと見た。
朔と、約束したことがある。
もうずいぶん前のことのように感じるが、実際は一昨日のこと。
この首吊り事件がひと段落ついたら、朔の師匠に会いに行こう、と。
銀花の両親を知るというひとに。
――では、このひとが。
止まった空気の中で、朔の師だというそのひとが一歩足を踏み出した、そのとき。
「三対一は、ちょっと不公平じゃないかなあ」