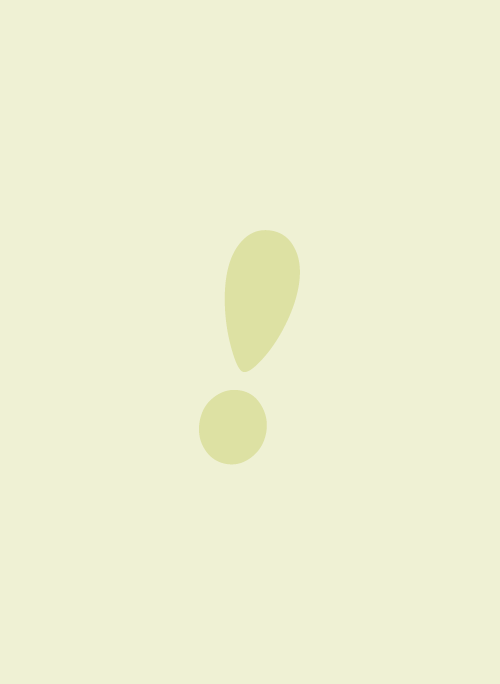「答えられないなら黙って見てろ。……俺は、こいつを殺すために、この十年を生きてきたんだ。邪魔をするならその狐ごとおまえも斬る」
ズキ、と、胸を刺すような痛みを感じて、銀花は顔を歪めた。
心を開いてくれたと思った。
仲良くなれたと思った。
笑ってくれることが嬉しかった。
けれど今、はじめて朔を怖いと思った。
風伯を斬ろうとしたときも、怖いとは思わなかったのに。
「朔……!」
こらえきれずに叫んだ声は震えていた。
呼んで、どうしたいのだろう。
戦うのをやめてくれと言いたいのだろうか。
猫目にそんなことを言わないでくれと言いたいのだろうか。
どちらも違う気がした。
――そうだ。
何かを言いたくて呼んだわけじゃない。
呼びたいから、呼んだ。
そうしなければ、このまま朔がどこかへ行ってしまいそうで。
銀花の声に、猫目と朔が振り返った。
二人の目が、一瞬、迷うように揺れる。
――そのときだ。