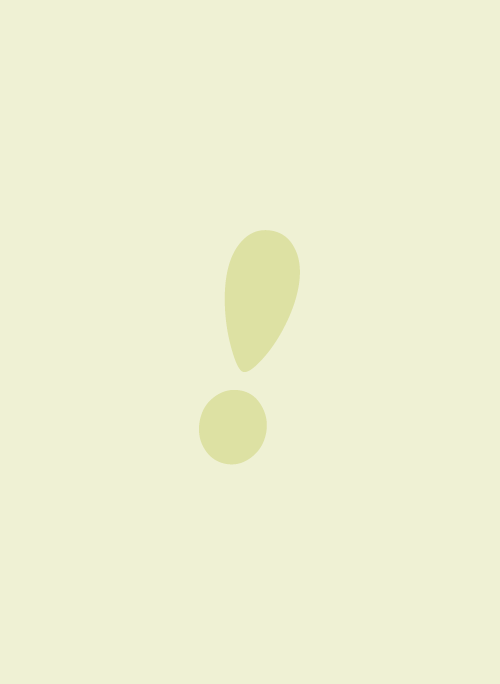朔が固まっていた。
振り下ろした炎の刃が晦を斬る直前で、その手は止まったまま動かなかった。
焦りと戸惑いを浮かべた朔の顔と、唖然とした晦の顔が蒼炎の刀を挟んで向かい合ったまま、二人は動けないでいた。
何が起きたのだろう。
そう思った、そのとき。
「駄目だよ、朔」
声とともに、朔の真後ろの木の枝から、猫目が飛び降りた。
いつの間にそこにいたのか。
朔も晦も、遠くで見ていた銀花でさえも、まったく気がつかなかった。
「猫目……? どういうつもりだ」
朔は動けないまま、目だけを動かして猫目を睨みつけた。
「殺しちゃだめだ。訊かなくちゃいけないことがあるから」
今様、おいで。
猫目は朔の言葉に答えると、口の中で小さくつぶやく。
すると朔の肩のあたりに、すぅっと白い狐の姿が浮かび上がる。
白狐が軽やかに跳んで猫目の方に移ると、朔は急に糸が切れたかのようによろめいて、刀を持った腕を下ろした。