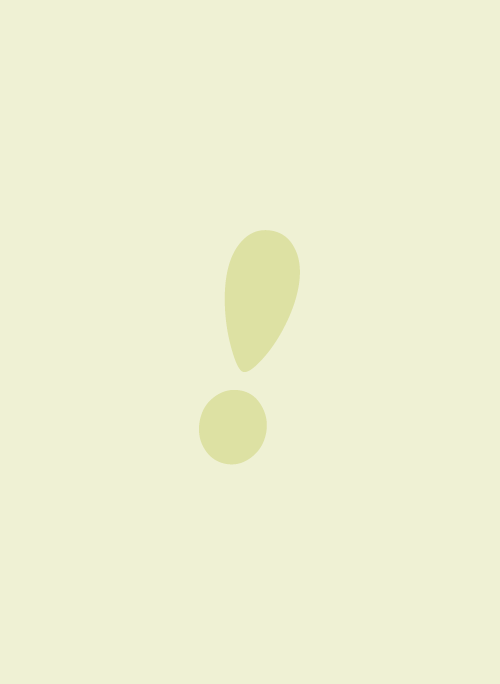「銀花」
無駄とわかっていてながら、朔は呼びかけた。
返事の代わりに、銀花の両目から溢れる、涙。
桜色の唇が震えて、朔を見ているのに朔を映さない瞳が揺れた。
「……し、ななきゃ……」
弱々しい声が朔の耳に届いた。
いつもは高く明るく響く彼女の声が、ひどく怯えて震えている。
「……死にたい、死ななきゃ……ひとりは、いや……」
「銀花、おい」
「どっちにもなれないのは、もういや。どっちにも嫌われるのは、もう、いやなの……」
ぶつぶつと、誰に言うでもなくただこぼれ落ちるその言葉を聞いて、なるほど、と朔は呟いた。
(なるほど、あれはそういう妖か……)