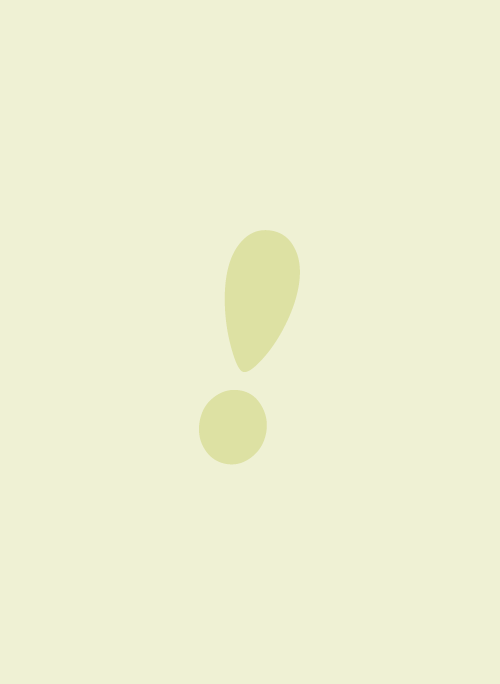朔の怒鳴る声にハッとした頃にはもう遅い。
鬼は銀花にそのままぶつかり、白い霧のようになって消えていった。
――いや、正確には、銀花の胸元に吸い込まれていった。
ゆっくりと、銀花の体が傾いていく。
朔は手に持った刀を素早く収めると、銀花を抱きとめた。
「おい! おい、銀花!」
気を失ってはいない。
目は開いているのに、その目に光はない。
何度呼びかけても、銀花の返事はなかった。
それを見て、朔は唇を噛んだ。
遠くから遠慮がちに視線を送る弥吉の父母は何が起きたかわからないだろうが、仮にも朔は退治屋。銀花がどうしてしまったのかくらいはわかる。
――鬼に、憑かれたのだ。