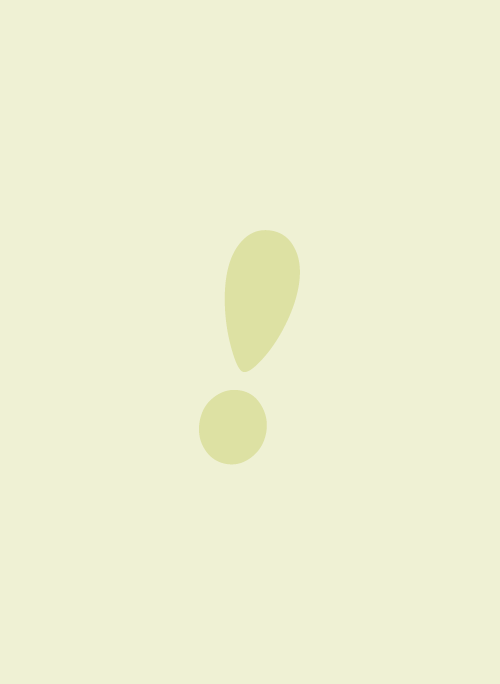「それが、あたし?」
「だろうな。その赤子の、人である母と、鬼である父のことをよく知っていたと言っていた。
その二人に託されて、赤子を祖母の元へ連れていった、と」
それは、ほぼ間違いなく自分のことだ。
まさか両親を知る人がいるなどとは夢にも思わず、銀花はただ口をぽかんと開けていた。
「首吊り事件がひと段落ついたら、……おまえが望むなら、師匠に会ってみるか」
両親のことを、聞けるかもしれない。
それは、幼い頃から何度となく望んで、その度に諦めてきたことだった。
「会って、みたい」
訊きたいことがたくさんある。
どんな人だったのか。どんな出会いをして、どうやって結ばれたのか。
――銀花を、愛していたか。