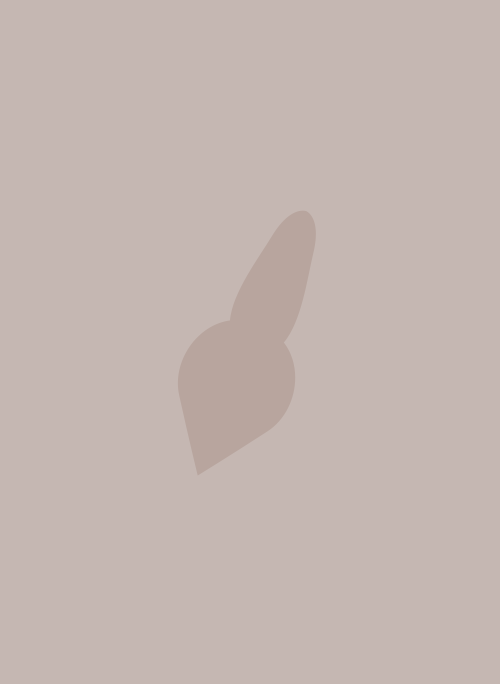「メイちゃん、嫌な話をさせてしまってごめんなさい」
「い、いえ…」
「でもね、これだけは言わせてください」
きゅ、と強めに抱きしめる。
「あなたは無価値なんかじゃありません。私、あなたといるだけで幸せですもの」
「一一っ、」
目を見開いた。
そんなことを言われたのは、“お兄ちゃん”以来だ。
「たぶんそれは、ルイさんもそうだと思いますよ」
「お、おれもだ!」
遅れてはならないとティンも言った。
「……」
嬉しいと、思った。
彼女たちは自分のために言葉を紡いでくれてるのだ。
こんな、役立たずのために。
「……ふぇ、」
泣きそうになる。
リルの暖かい胸の中で、感じたことのない母親の体温を必死に作り出した。
お母さんって、こんな感じなのかなと。
「…リルさん……あの、その…」
何を言えばいいのかわからないけれど。
「ありがとうございます…」
お礼ごときでつたわるだろうか。
この、心の満たされ具合が。
「いえいえ。私は本当のことを言ったまでです。
あなたは自分が愛されてることを信じてください」
初めて言われた言葉を反芻する。
愛されてることを、信じる一一
「小動物のような愛らしさを持った…」
「なんか色々台無しだぞ、リル」
なんの話をしてるのかわからないが。
楽しそうなので、泣く場面ではないと察した。