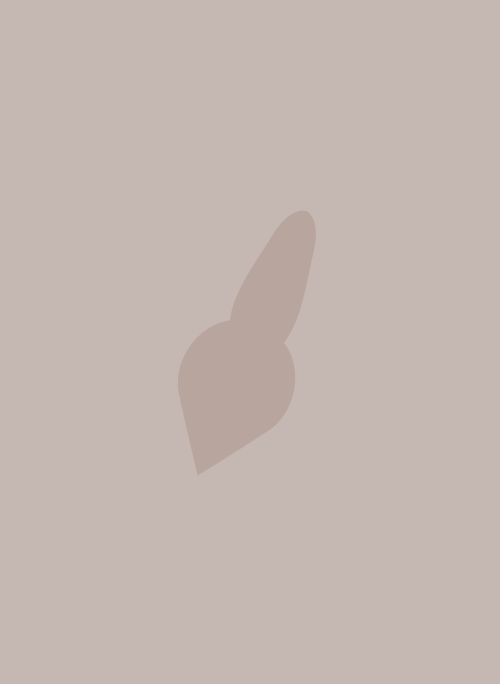◇◇◇
昼前の社長室、秘書である野崎の顔が真っ青になった。
「…しょ、正気…で、すか?」
「もちろんだ。お前を信用して頼んでいる」
「私、護身術等を持ち合わせていないのですが…」
「高校の時ソフトボール部だったのだろう?」
「申し訳ありませんが、ソフトボールは格闘技ではないのです…!」
いつも冷静な野崎とは懸け離れた、責任を放り投げる発言だった。
「普通のマンションですよ、社長!」
「だからこそだ、相手も油断する」
「失礼なんじゃ…」
「むしろ喜ぶのではないか?そういうのが好きそうなタチだ」
「…社長は変なところで妥協しますよね。母国のお姫様ですよ…?」
そう、野崎にはルコーラが帰っている間、リルとティンを預かってくれるように頼んだのだ。
仮にも一国の皇女だ、荷が重すぎると野崎は全力で断った。
「そういえば、社長…メイさんはどうなさるおつもりですか?」
「それが悩みどころだ、どこかの警備体制が万全のホテルに預けるとか…」
「………」
まさかの、メイの方が手厚い。
無意識なのだろうが、これは一国の皇女を預かっていて無責任というものだ。
昼前の社長室、秘書である野崎の顔が真っ青になった。
「…しょ、正気…で、すか?」
「もちろんだ。お前を信用して頼んでいる」
「私、護身術等を持ち合わせていないのですが…」
「高校の時ソフトボール部だったのだろう?」
「申し訳ありませんが、ソフトボールは格闘技ではないのです…!」
いつも冷静な野崎とは懸け離れた、責任を放り投げる発言だった。
「普通のマンションですよ、社長!」
「だからこそだ、相手も油断する」
「失礼なんじゃ…」
「むしろ喜ぶのではないか?そういうのが好きそうなタチだ」
「…社長は変なところで妥協しますよね。母国のお姫様ですよ…?」
そう、野崎にはルコーラが帰っている間、リルとティンを預かってくれるように頼んだのだ。
仮にも一国の皇女だ、荷が重すぎると野崎は全力で断った。
「そういえば、社長…メイさんはどうなさるおつもりですか?」
「それが悩みどころだ、どこかの警備体制が万全のホテルに預けるとか…」
「………」
まさかの、メイの方が手厚い。
無意識なのだろうが、これは一国の皇女を預かっていて無責任というものだ。