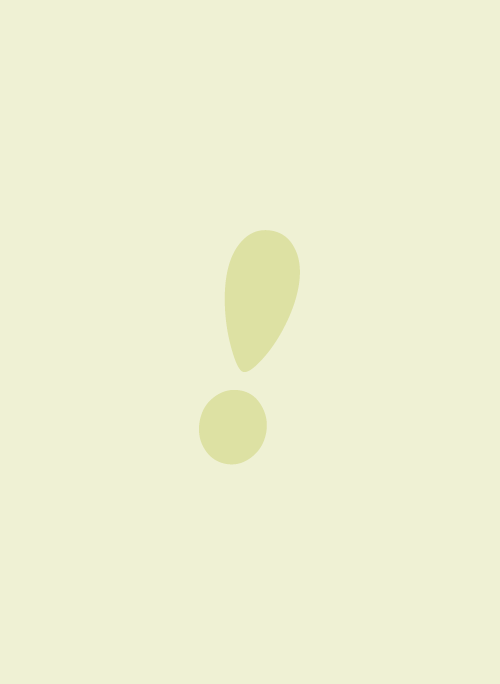かすれた声が耳に届き、それと共にアスラの意識は覚醒した。
「……はは、うえ」
唇が震えて上手く動かない。
ナズリの手がゆっくりと持ち上がり、アスラの方へ伸びる。
アスラはその手を両手で強く握った。
「母上、なぜですか……」
ナズリを見下ろして、アスラは言う。
不思議と涙は出なかった。
「なぜ、飲んだのですか。わかっていたはずなのに」
なぜ、自ら死を選ぶようなことをしたのか。
「あたしを、置いていくのですか」
言って、アスラは深くうつむいた。
――結局、自分のことか。母の死の際に、心配するのは自分が一人になることなのか。
己れの心の醜さに、どうしようもない嫌悪感がアスラの心を覆う。