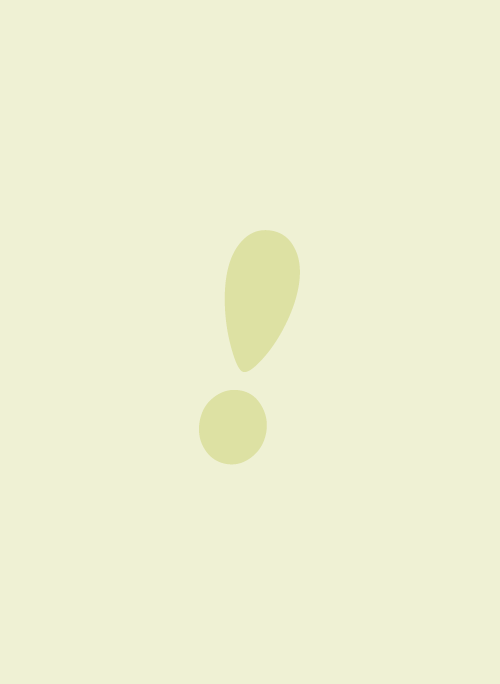「……すっげぇばかみたいだけど、まぁ、けっこうスッキリした」
不服そうに、ぼそぼそとそう言った。
一度言ってしまえば強がることに諦めがついたのか、シンヤは雪が解けるように柔らかく、その目を細める。
ずっと年に似合わない険しい表情を浮かべていた顔が、相応の幼さを取り戻した。
「思い出すだけで笑えてくる。とくに、あんたに首絞められそうになった時の領主の顔!」
「な! あれは傑作だった」
少女と少年は二人、領主の寝台に腰かけてケラケラと笑う。
用を済ませて戻ってきたイフリートに急かされても、アスラは帰ろうとはしなかった。
それどころか、〈イウサール〉の者たちと一緒に領主の家財を漁りはじめる。
豚の血を買ったり娼婦を丸め込んだりで結構出費が多かったんだ、ここで稼いでおかないでどうする。
そう言って笑ったアスラに、そういうのは「稼ぐ」とは言わない、と、イフリートはいつものようにため息を吐きながらも、結局はアスラのすることを止めようとはしないのだ。
砂漠の町の夜は、そうして更けていく。
その静けさの中に、小さな嵐を呑みこんで。