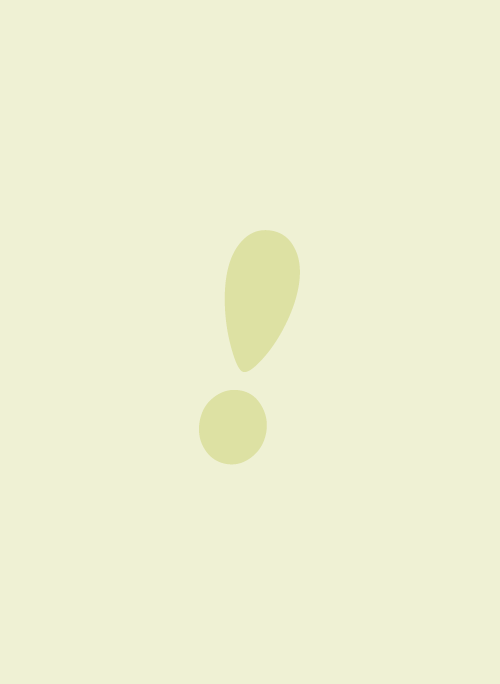領主の話に適当に相づちを打ちながら、どんどん酒を勧める。
優雅で気品のあるただずまい、教養をうかがわせる気の利いた返事、どこか気の弱さを感じさせる微笑み。
すべて、王女であるアスラにとっては、幼少の頃よりたしなみとして叩き込まれてきたものだ。
(王族の女なんて、結局は他国の王子に身を売る娼婦のようなもの)
その証拠に、王女の身でありながら娼婦の真似事をする己を、恥ずかしいとも思わない。
そう思ってアスラが皮肉な笑みを浮かべた頃には、領主は足元も定まらないほどに酔っていた。
巨体をふにゃふにゃと動かして、領主はアスラの肩に手をかける。
呂律のまわらない舌を無理やり回して、「ミナ、そろそろ……」と、酔って耳まで赤くなった顔をアスラの顔に近づけた。
背筋を這う気色悪さをこらえながら、アスラはにっこりと笑って、その手を逃れる。
「その前に、カーテンをお閉めになりませんと」
立ち上がって、窓辺へ歩いていく。
カーテンに手をかけながら、アスラは黒髪を束ねた紐を片手ではずした。
――それが合図だ。