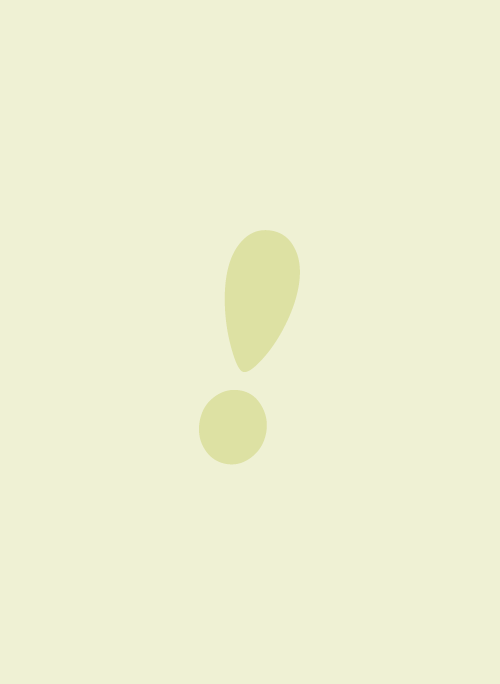「病気の母親を養う健気な息子なんてのは、最低限住む家と職があってから成り立つ話だ。
スラムで生きてる俺らは自分が生きるので精一杯。
体が弱いヤツなんてのは、真っ先に死ぬ。誰も養う余力なんてねぇ」
嘲るように歪んだ笑みを浮かべたシンヤが吐き捨てるように言う。
「おまえら金持ちはそのへんがわかってねぇから、こんな嘘にコロッと騙されるんだよ」
幼い顔に似つかわしくない暗い目をした目の前の少年に、アスラは痛ましげに顔を歪めた。
「それほど達観したおまえが、なぜ仇なんて……」
スラムで生まれ育った故に人の死を諦念と共に受け止める心の用意ができていた彼が、それでも許せないと思うだけの理由は、何なのか。
そう問うと、シンヤは眉ひとつ動かさずに淡々と答えた。
「母ちゃんは去年の暮れに、領主の馬車に轢かれて死んだ」
「……事故、ではないのか?」
「違う。道の真ん中で転んで、足が弱くてすぐには立ち上がれなかった母ちゃんを、領主は馬車を止めて待つこともせずにそのまま轢いた。
母ちゃんがいるのに気づいていたのに、だ。
もちろんその後、領主はお咎めなし。墓を作ってやることもできず、母ちゃんの亡骸は役人に燃やされた」