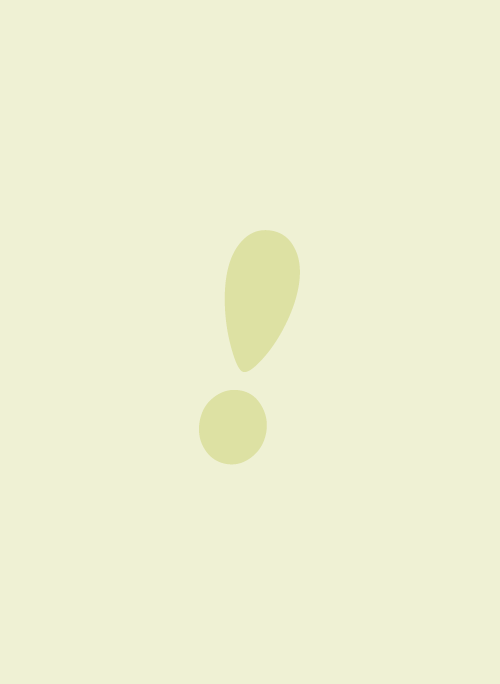だが、アスラは偽の名を名乗るつもりはなかった。
王宮を出たときから、それは決めていた。
「アスラだ」と、正直に答える。
姓さえ名乗らなければ、誰もアスラ王女だとは思うまい。
アスラという名の女は、この国では珍しくないのだ。
そう思っていたのだが。
「やっぱり、アスラ王女殿下だったのか」
男の言葉に、アスラは再びうんざりしたような顔をする。
そして、否定しようと口を開いた、そのとき。
男がアスラの手を取って――その手の甲にそっと口付けた。
「あ、え…………はぁっ!?」
アスラの口から否定の言葉ではなく、頓狂な声が漏れた。
その顔がみるみる赤くなる。