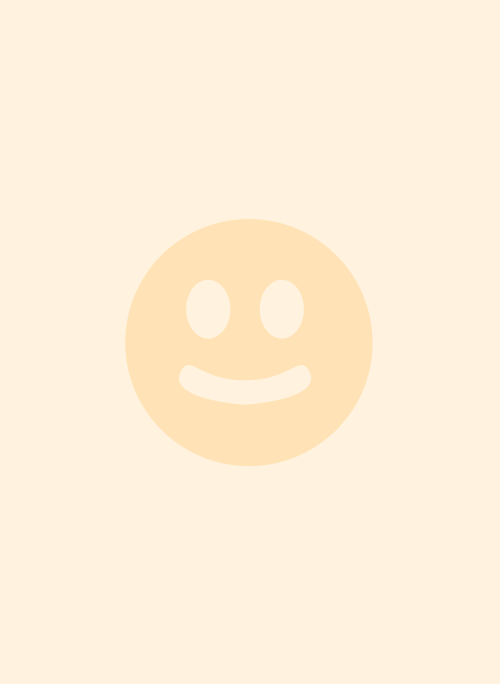しかし、戸口は外側から閉められていて、とても優菜の力では開けられない。
「待てと言うに」
男は優菜の肩にそっとを置くと、
「まあ話を聞け。
そなたのことは丁重に扱ってやる」
と囁いた。
葉擦れの音に似た、静かな声だ。
不思議なことに、あれだけ焦っていた優菜の心はいつの間にか落ち着き、気がつけば男に向かい合って正座していた。
優菜自身、まるで催眠術にでもかかったようであった。
「儂(わし)の名は漣(さざなみ)。
ここらの山々を支配する、妖の頭領よ」
漣という男は、自らの胸に手を当てて、そう名乗った。
「あや、かし?」
「妖怪の仲間と思えばよい」
漣はうなづいた。
優菜は、この神社の化け物伝説を信じてはいるが、妖怪という現実味のないものを信じたことはない。
ゆえに、漣の言うことには思わず息を飲んだ。
彼がただの和装の男だと思いたいが、その目の色、牙、周囲を取り巻く謎の炎が、なによりの証拠となっている。
「儂はな、今年で千歳を超えるのだ。
妖とて寿命はある。
だか、儂には世継ぎがいなくてな」
「はい……」
「世継ぎを持つためには、どこかの女と契らねばならぬ。
儂はここ数日、我が妻となる女を探しておったのだ。
そこで、そなたを見つけた」
漣は妖艶かつ鋭い瞳で優菜を捉える。
ここで優菜は、漣の言いたいことを理解した。
案の定、漣は優菜の手を持ち上げると、そこに唇を這わせた。
「儂の女になれ、平坂 優菜よ」