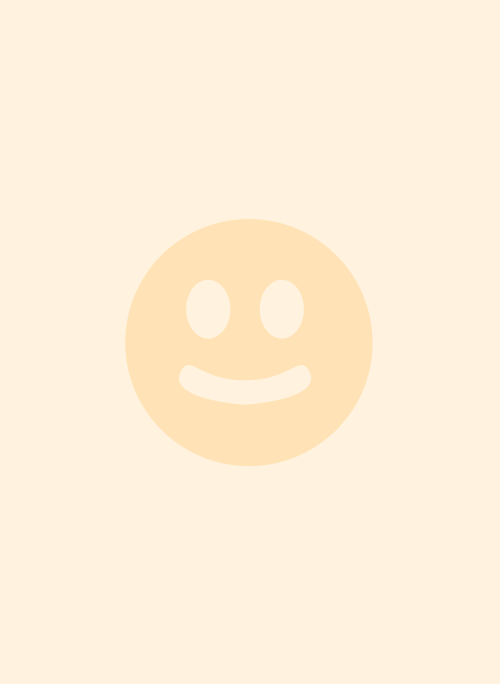「生ける者の血に濡れし、白絹の女。
まさに我が妻にふさわしい」
男は形のよい唇を吊り上げ、嗤う。
「娘よ、名をなんと申す」
男はやけに古臭い言葉で問う。
眼前に現れた奇怪な男に、優菜は戸惑いを隠せない。
「ひ……」
「うん?」
「平坂(ひらさか)優菜、です……」
消えいらんばかりの声で、優菜は名乗った。
「ふむ、優菜か」
男は優菜の顎に手を添え、じっと優菜の顔を眺める。
鋭敏な美貌だけに、男は迫力がある。
御堂の奥に、入り口はないはずだ。
それなのにこの男は、御堂の奥から現れた。
少なくとも、優菜が入れられた時にはいなかったはずである。
「あの、貴方は……」
優菜が不審に思って口を開くと、男はその長い人差し指を、優菜の唇に当てた。
「案ずるな。
そなたに害は加えぬ」
男は言うなり、にい、と歯を剥いた。
優菜は慄然とする。
その口には、びっしりと揃った鋭利な牙が生えている。
ヒトのような四角い歯ではない。
まるで獣のような、鋭い牙だ。
「ひっ」
優菜は押し殺した悲鳴を上げる。
この神社が化け物を祀っているという話は、子供でも知っている。
もしかすると、彼はその化け物か。
優菜は震える体に鞭をうち、必死で戸口へと手を伸ばす。