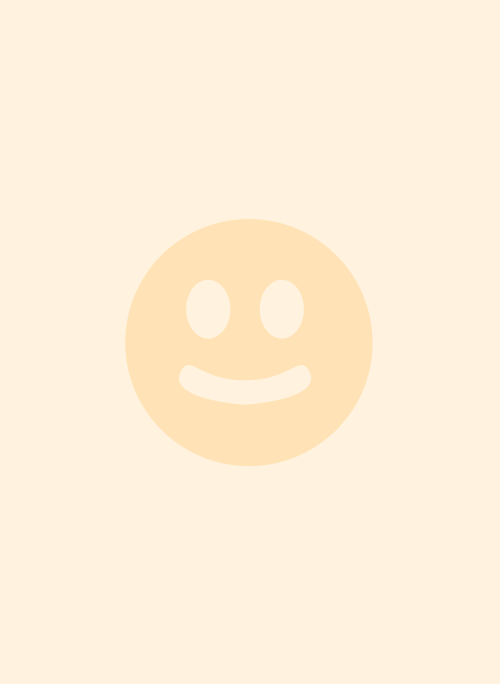*
不思議なことにーーー帰る時、池の水鏡を覗き込んで見ると、そこに映っていたのは、そこらの人間と変わらない肌と、黒い瞳を持つ自分だった。
化け物のような姿が、嘘のようだった。
それから無事なにごともなく塔に帰り、そしてこっぴどく叱られたのを、嶺子は覚えている。
大人たちの咎めを受けても、へこたれなかった自身のことも、覚えている。
『人に優しくする方法を、教えてください!』
そう、強く頼んだことも。
“力”を制御する訓練も、二度と怪物に変身しない努力も、嶺子は全て鮮明に覚えていた。
あの湯豆腐を箸で持ち上げようとしているような、難易度の高い訓練は、無駄にはなっていない。
二十年という歳月が経ち、いま、その訓練が役に立っている。
洗面台の鏡に映った、鋭敏な目つきの自身を見つめて、嶺子は少しだけ、唇を釣り上げた。
仕事終わりの体は、じっとりと汗ばんでいる。
仕事着を脱いでTシャツを着ると、嶺子は忍び足で寝室に踏み入った。
時計の針は午前二時を指している。
当然ながら、部屋の中は咫尺を弁ぜぬ闇だった。
しかし、嶺子には部屋のなかがはっきりと見える。
ふたつ敷かれた布団。
そのうちのひとつが、ちんまりと盛り上がっている。
そこから出ている小さな顔の前に、嶺子はしゃがみこんだ。
「陽頼、ただいま」
布団の中で、最愛の恋人がお日様のように微笑んだ。
【終】