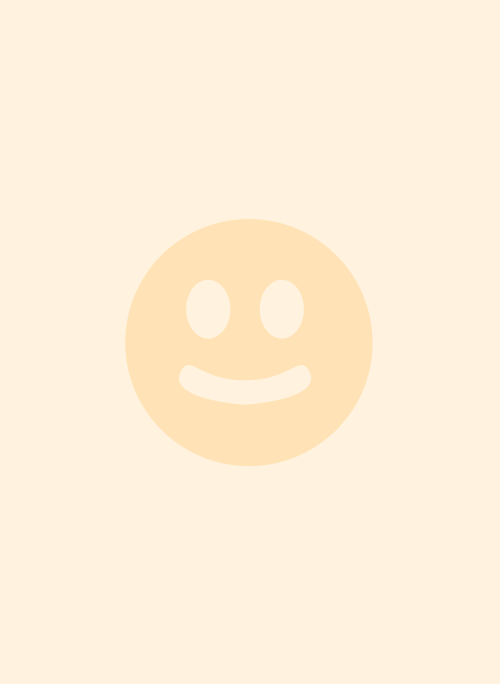「夏とか、用水路にオタマジャクシがでるんだけど。
私、オタマジャクシを捕まえようとして、握りつぶしちゃったことがあるの」
顔の前で拳を作って見せ、少女はすまなさそうに眉を下げた。
「でも、優しく手で掬ったら、オタマジャクシ捕まえれたんだ。
優しくやればいいんだよ」
少女は水を救うように手を合わせる。
「それにきみ、意地悪そうに見えないし」
頬杖をつく少女は、そっと嶺子の顔に手を添えた。
血が通っている。
熱がある。
暖かい。
嶺子はじんわりと伝わるものに、しびれるような何かを感じた。
「……」
口の中に残る甘い味と、右頬を包んだ温もりを噛み締めているうちに、嶺子はまた、涙をこぼしていた。
あれだけ罵られ、大人から暴力を受け、異質な自分を嫌いになり、怯え切っていた嶺子にとって、この温もりは甘美な蜜のようだった。
「よしよし」
少女は自分のコートの袖を嶺子の頬に当て、涙を拭ってやる。
「うん……うん……」
しゃくりあげながら、嶺子は何度もうなづいた。
これは、自分を異質な生き物でもなく、気持ちの悪い化け物でもなく、同い年の人として扱ってくれる手だ。
絵本に見る、顔のついたお日様のような。
「陽頼(ひより)ー?」
不意に、外から女の声か飛んできた。
「ママ!」
少女は勢いよく立ち上がり、障子窓をからりと開け放つ。
外から白石を踏みしめて、背の高い黒髪の女が荒屋に近づいてくる。
どうやら少女の母らしい。
「じゃあ、私いくね」
少女はにこりと振り向きざまに微笑むと、一歩踏み出そうとした。
「ま、まって!」
嶺子はとっさに声を上げる。
ーーー上げたはいいが、そこで怖気付いた。
小心なだけに、大きな声を上げるのは苦手だ。
それでも嶺子は、決死の思いで声を振り絞った。
「ま、また、ここにきてくれる……?」
ごくりと固唾を飲み、嶺子は少女を見守る。
彼女は本当に笑顔の多い少女だった。
陽だまりのように笑って、「うん」と手を振った。
「またね」