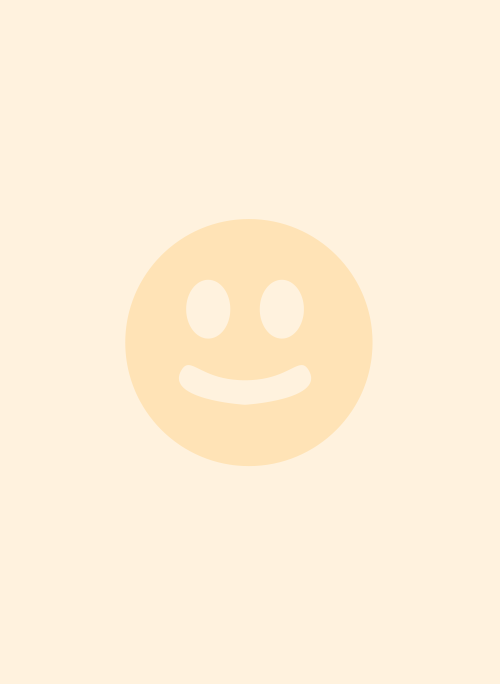まだ幼い、少女の声だ。
その少女は唐突に、家の玄関をからりと開けた。
ノックをしないのも当然だ。
荒屋のうえ、誰がどうみたって人が住んでいる様子はない。
誰もいない襤褸屋に、ノックは必要ない。
「あっ……」
嶺子は慌てて隠れ場所を求めた。
しかし、この和室には隠れられる場所がない。
唯一ある押し入れも、襖が倒れていて中が丸見えだ。
隠れようがない。
嶺子はあたふたするばかりで、そこから動くことができなかった。
そうしている間にも、足音は床を軋ませてやってくる。
そしてとうとう、からりと戸が開けられた。
「わ」
開け放たれた戸の先で、少女が小さく声を上げた。
コートを着込み、ニット帽をかぶったツインテールの少女である。
肩からは小さな黄色のポシエットを下げている。
年は嶺子と同じか、それより上かと言ったところで、大きな丸い目が可愛らしい少女だった。
「ひっ……」
嶺子は身を竦ませ、とっさに腕で顔を庇った。
「こっ、来ないでっ」
嶺子は叫んだ。
しかし戸口の先に立つ少女は、なんのことかと首を傾げるばかりで、立ち去る気配もない。
「帰ってよ!」
嶺子は鼻声でいまいちど叫んだ。
だがその直後に、ぐるる、と間の抜けた腹がなる。
「どうしたの?
お腹空いてるの?」
嶺子の漆黒の肌には目もくれず、少女はそう訊いた。