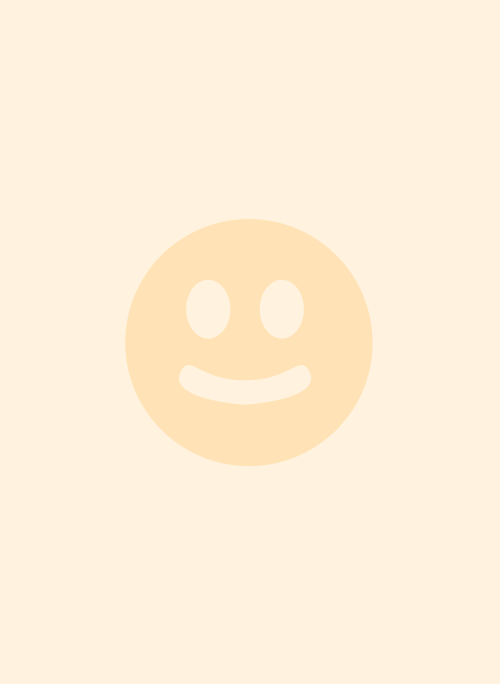それからどれくらいの時間が経ったかは定かではない。
少なくともサナにとっては、その時間はひどく長かった。
事を終えて、服を着て、そしてある程度ぼうっとしていた少年は、
「ん」
と、剥ぎ取った少女の装束を無造作にサナにかけて、さっさと部屋の外へと出て行った。
やっと、嵐が過ぎ去ったような気がした。
「はあ……はっ……う」
じっとりと汗ばんだ身体に装束を巻きつけ、少女は九尺二間ばかりの小さな部屋の中を見渡した。
しかし涙で視界がかすみ、自らの血で汚れた布団さえまともに見えない。
「うう……あ……」
サナは僅かに声をあげ、むぜひ泣いた。
腰が痛い。
腕も痛い。
それなのに嬲られている最中、弱々しく喘いでしまったことが、なにより情けない。
いまはもう過ぎてしまったとしても、またすぐに、同じ行為を強いられることとなるだろう。
生きた先には、地獄しかない。
生き延びろと母ひ言ったが、これではむしろ、死んだ方がましというものだ。