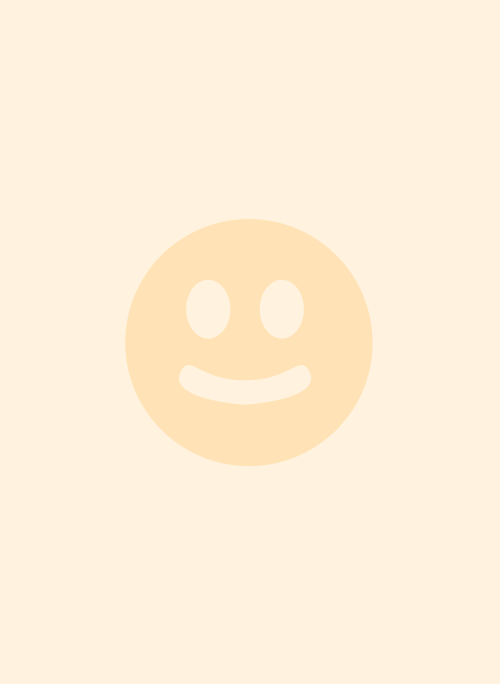「いいのよ、まだ“力の加減”が難しいんだから。
新しいのと、とりかえっこしましょうね」
科学者風の女は微笑むと、新しいスプーンを少年に渡し、少年の噛み跡がついたスプーンを手に取った。
ーーーこの建物には、白衣の人間しかいなかった。
いつも少年が壊した玩具や、箸、スプーンを持って行って、数人で集まる。
そしてなにやら真剣な顔で、グラフや、奇妙な赤と青の螺旋が描かれた紙を手に話し合っている。
「素晴らしい。
鬼と人の子が、これほどまでに強い力を持っているなんて」
「新発見だ。
人と鬼の血が混じった子供は、鬼をもしのぐ力を得る」
白衣の大人たちは、そんなことを言っていた。
少年にはなにひとつわからなかった。
大人たちが言っていることの意味も、彼らがなぜ自分を見張っているのかもだ。
少年の名を、酒童嶺子(すどう れいじ)という。
ほっそりとした体型に、明るい茶髪の子供だ。
健康的な肌の色で、あまり他の子供と変わったところはない。
だがその眼は鋭く、子供ながらに酷い目つきの悪さだった。
しかもその瞳は、日本人を思わせない碧眼である。
まるで極悪人の子供のような顔をしているが、嶺子はこれでまだ五歳だった。