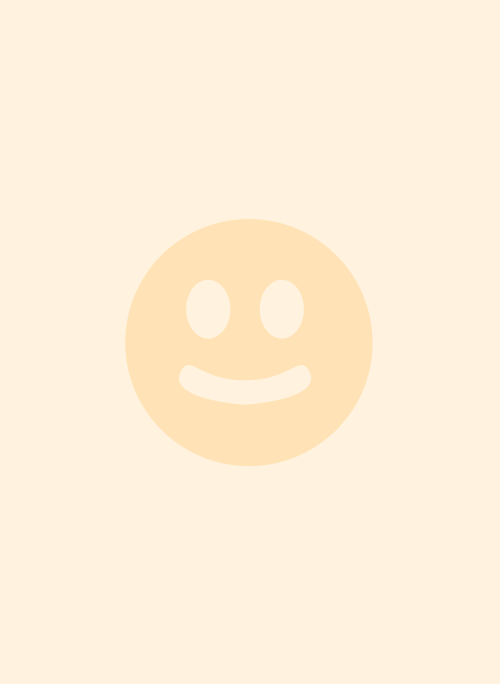魔法使いは家に帰り、白雪姫ほブーツを脱がせてベットに寝かせてやる。
当然ながら、魂の抜けた身体は無抵抗にベットへと転がり、仰向けに横たわった。
(やれやれ)
世話の焼ける死体だこと。
魔法使いは鼻を鳴らし、そっと白雪姫のうすい唇にキスをした。
すると、ぱちり、と白雪姫が目を覚ました。
まるで、いまのいままで昼寝をとっていたかのように、だ。
「ふがあ……」
女っ気のない欠伸をし、白雪姫はベットの上で胡座をかいた。
そして翡翠にも勝る碧眼をちらつかせ、眼前にいる魔法使いに目をやった。
「あれ……」
俺、どうして。
白雪姫はつぶやいた。
死んだはずの自分がなぜ生き返ったのかを疑問に感じているらしい。
そして白雪姫は胡座をかいたまま、「誰だい」と魔法使いに問いかけた。
「暗き森の魔法使いさ。
心臓を食べると専らの噂のね」
「魔法使い?」
「君を魔法で蘇らせたのも、私だよ」
魔法使いは妖艶に微笑んで見せる。
しかし白雪姫は、目の前の魔法使いに毛ほどの恐怖心もないようで、下品にも耳の穴に小指を突っ込んだ。
そしてにこりと歯を出して笑うと、
「へえ、お前が助けてくれたのかい」
と、心底から感謝をしたふうに言葉を漏らした。
「ありがとう、森の魔法使い」
礼を言われて、魔法使いは拍子抜けした。
怖がらせるつもりで「心臓を食べる」と前置きをしたのに、白雪姫は怖がるどころか、呑気に自分が死んだ経緯を明かしている始末であった。
ーー白雪姫の家系は男に恵まれなかった。
しかもこの白雪姫に関しては、男の美しさは持っているくせに、女の美しさはこれっぽちだって持ち合わせてはいなかった。
当然、そんな男姫と契ろうなどという男は、どこの国だっていやしない。
女が王位を継承することが許されないご時世、嫁の貰い手もなく、城に居るだけの白雪姫は、王の後妻にとっては目の上のたんこぶだった。
王の後妻の娘はみな美しく、才色兼備である。
しかしその娘たちは王族の娘であり、王女……つまり王の長女ではない。
自分の娘を王女にし、場内での自分の地位を上げるためにも、後妻には白雪姫が邪魔だった。