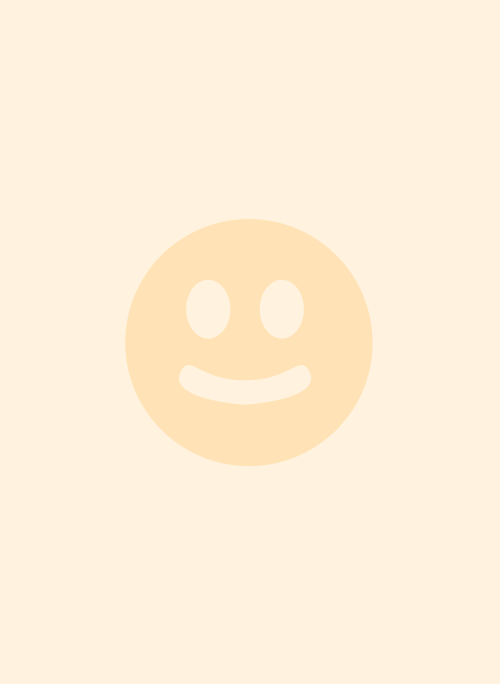しかし遺伝上の父である傭兵は、マスラの漆のような黒髪と紅い瞳を気に入り、生かしておく選択をとった。
それから一人前の兵士になるまでの十三年間を訓練所で過ごし、苛烈な偏見にまみれながら今まで生きて来たのだ。
マスラの善意とは反対に、身体は数々の悪行に走った。
戦場で残忍な殺傷だってした。
そしてまた、ことが終わってから正気に戻る。
まるで地獄のようなそれをただ、繰り返した。
悪行に及んでいる最中も、マスラの意識はあった。
嫌だ、やめろ、やめてくれ。
マスラがどれだけそう願っても、身体は言うことを聞かなかった。
そのくせ、無意識のうちにマスラは罪悪感などわすれて、時に快感さえおぼえてしまう。
そしてまともな意識が戻ると、当時の記憶が鮮明に蘇るのだ。
殊に、今回はーーーー。
「……ご、めん……」
マスラは顔を手で覆い、連れてこられた少女に向けたつもりで、そう言った。
消えいらんばかりの声であった。
まだ生娘だったろう。
男など知らなかったろう。
きっと好きな人がいただろう。
そんな少女を、自分は助けるどころか、さんざん嬲りものにした。
自分が、彼女のなにもかもを奪ったのだ。
嫌だと懇願する声を無視して、押し黙らせて……。
兵舎を出た後も、少女のすすり泣く声が聞こえて、それが胸を抉った。
いまはまともな意識があるとしても、また兵舎の戻れば、同じ苦しみをまた与えることになる。
それを思うと、とても兵舎には戻れなかった。