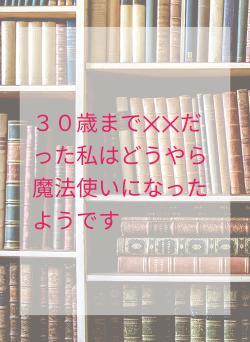後方を確認してみても、そこには人の顔のようなシミや汚れは見当たらなかった。
ただ、灰色の塀が広がるばかりだ。
ゾクリ。
また、あの寒気が背筋を撫でていく。
あたしは身震いをして塀から離れた。
「大丈夫か?」
知樹があたしの肩を抱いてくれるが、一向に寒気は消えてくれなかった。
結局、あたし達はそのまま家に帰ることになってしまった。
あの写真を見た後じゃ、直弘も口数が少なくなっていた。
「大丈夫だって、気にし過ぎはよくない」
知樹が家まで送ってくれた別れ際、そう言ってあたしの頬にキスをした。
嬉しいはずなのに、あたしの心は沈んだままだった。
ただ、灰色の塀が広がるばかりだ。
ゾクリ。
また、あの寒気が背筋を撫でていく。
あたしは身震いをして塀から離れた。
「大丈夫か?」
知樹があたしの肩を抱いてくれるが、一向に寒気は消えてくれなかった。
結局、あたし達はそのまま家に帰ることになってしまった。
あの写真を見た後じゃ、直弘も口数が少なくなっていた。
「大丈夫だって、気にし過ぎはよくない」
知樹が家まで送ってくれた別れ際、そう言ってあたしの頬にキスをした。
嬉しいはずなのに、あたしの心は沈んだままだった。