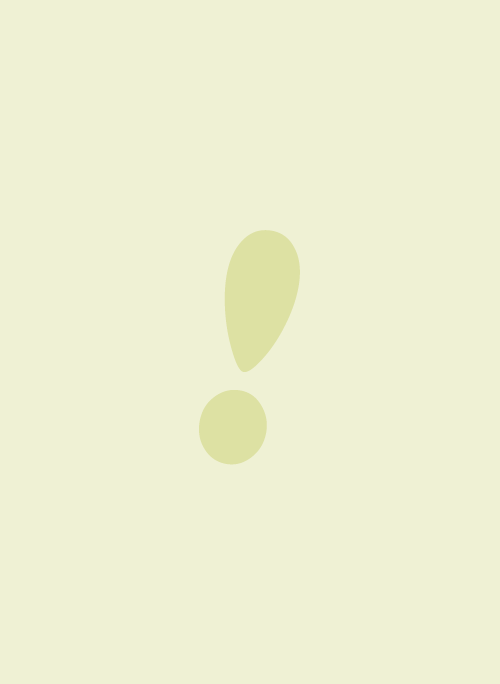するとふいに、ミオがエルを見た。
幼い大きな目がまっすぐにエルを捉える。
その目をエルが見返したとき、ミオは唐突に「あっ!」と声を上げると、母親の腕から降りて野営地へ走っていってしまった。
「あ…………」
吐息とも呟きともつかない声が口からもれる。
怖がらせてしまったのか。
そう思って、エルはうつむいた。
だが、小さな足音はまたすぐに戻ってきた。
そしてうつむいたエルの顔を覗き込み、あどけない顔いっぱいに笑顔を浮かべる。
ミオは小さな手をエルにまっすぐに伸ばした。
「これ、あげる!」
受け取ってみると、きれいに磨かれた鈴だ。
曇りのない銀色に、エルの赤い髪が映りこむ。
「これを、あたしに……?」
エルは半ば呆然としながら、ミオの目を見返した。
ミオは大きく頷いた。母親と同じワインレッドの髪が勢いよく跳ねる。
「ミオのたからものなの。わるいものからまもってくれる、おまもりなんだよ。
おねえちゃんがみんなをまもってくれたから、ミオからのおれい!」
おれい。お礼。に、宝物をくれたのか。
「おねえちゃん、ありがとう!」
エルを見上げて明るく笑うミオの顔に、透明な水が一滴、ポタリと落ちた。