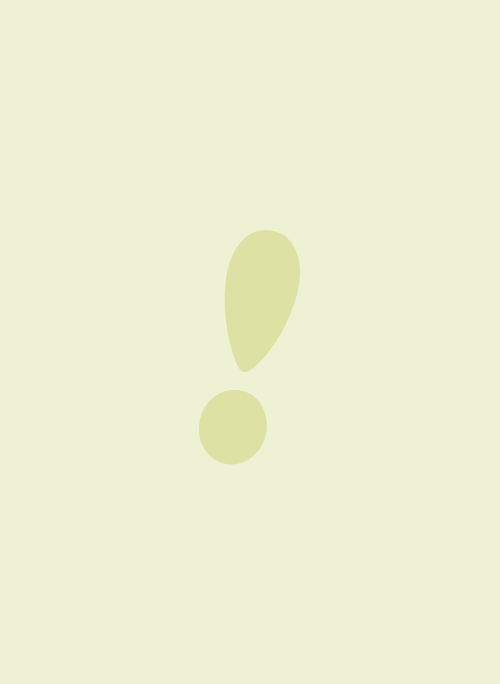「そのウィオンの人々は皆、緑の髪をもつようです。わたしもウィオンからの移民でしたし、エルマ様も、あるいは。……わたしもあなたくらいの年の頃は、自分の髪が人と違うことを気にしたものでしたから、お話してみました。余計なお世話でしたら申し訳ありません」
フシルは微笑んで言った。エルマはあわてて首を振る。
「とんでもない。ウィオンには一度行ってみたかったが、その話を聞いてますます行きたくなった。もし無事にルドリア役を終えてアルに帰れたら、行けないかどうか本気で考えてみるよ」
エルマが言ったとき、ちょうど鐘楼から重々しい鐘の音がした。晩陽の鐘だ。
「ずいぶんと長いこと話し込んでいたみたいですね。夕餉の支度もそろそろできるでしょうし、居館に戻りましょうか」
言って、フシルは立ち上がる。その彼女を、エルマは「あ、最後にもう一つ」と言って呼びとめた。
「はい?」
「リヒターに勝ちたくて努力したと言っていたが、結局リヒターには勝てたのか?」
エルマの問いに、フシルは静かに首を振った。
「いえ、実のところ、いまだにリヒター王子との二戦目を果たしていないのです。
近衛隊で十年もやってきたものですから、リヒター王子に勝負を挑むなどという恐れ多いことが、今のわたしにはどうしてもできないのです。もう一度、王子と手合わせをしてみたいと思ってはいるのですが……」