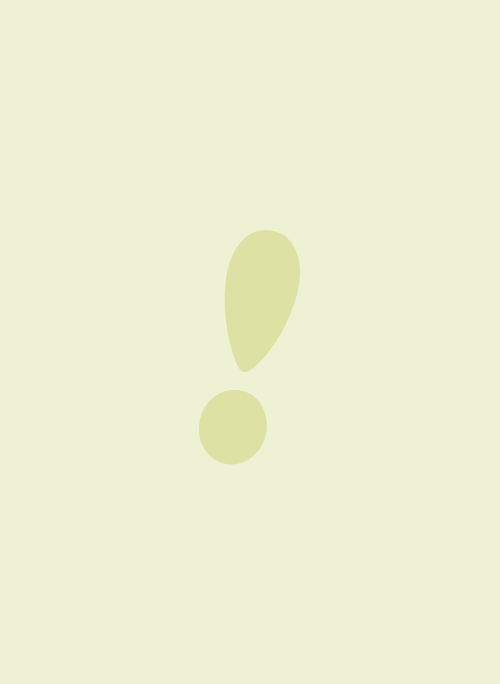ああ、と、小さなため息が漏れた。
(どうして、ラグもじいさまも、わたしが欲しい言葉をくれるんだろうな)
そう思ったとき、唐突に思い浮かんだのは、幼い頃の記憶だ。
あれは、確か、エルマが七つになった頃のことだ。
大陸のとある国の、そのときも森の中の野営地にいた。
カームにとの槍の稽古が終わって、へとへとになったエルマに、近くの川で汲んできた水を差し出してくれたのはラグだった。
そういえば、水を運んできてくれるのはいつだってラグだ。
そう思い至ったエルマは、ラグから水を受け取るときに、「いつもごめんね。ラグだって、今いろいろとやることがあって大変なのに」と言った。
当時、アルの民の一員になったばかりの十一歳のラグは妹の面倒を見ながらも、いろんな人について回っては、
剣や槍、弓矢に、それらの武具の手入れの仕方、獣の捕らえ方やほつれた服や靴の直し方、天幕の張り方など、
武術やその他のアルで生きていくために必要なことを余さずすべて学びとろうとしていたのだ。
エルマよりもへとへとなはずのラグは、しかし、エルマの詫びに笑顔を見せて、
「そんなのいいんだ、エルマ。好きでやっていることだから。それに僕、『ごめんね』よりも『ありがとう』が欲しかったな」
と言った。
エルマは慌てて「ありがとう」と言い直した。
ラグの笑顔を眩しいと思った。
アルに来るまでのラグがどんな生活をしてきたかを、そのときのエルマは知っていた。
それが、ラグ本人が汚らしいと言って、どれだけ忌み嫌った暗い過去であるかも。
それでも彼の笑顔は太陽のようだった。
そんなラグが、エルマが数えで十五になったとき――エルマが新しいアルの長になったときに、言ったことがあった。
「僕はこれから、もっといろんなことを学んで、長としての君を支えられるように頑張るよ。
君が困ったときは、いつだって僕が支えると、約束するよ、エルマ」と。
それ以来、彼はエルマを名前で呼ばなくなった。
彼はエルマに敬語を使うようになった。
その変化を嬉しいとも、寂しいとも思ったが、同時に、「がんばれよ」と背中を押されているような気がして、身の引き締まる思いがした。