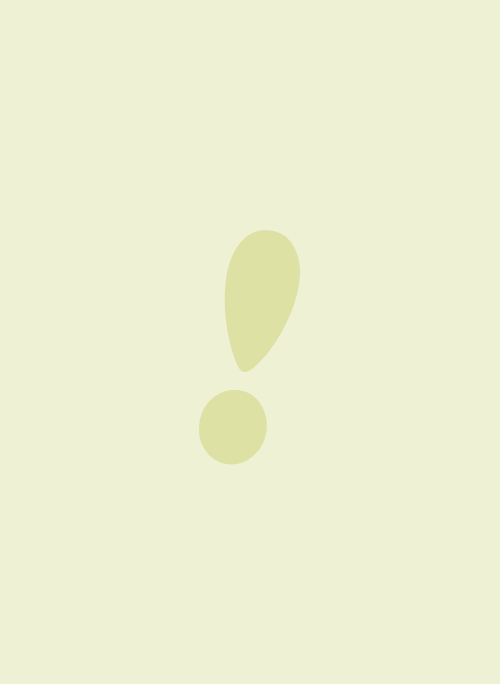耳元で囁かれた言葉に、メオラは大きく目を見張る。
「行かないでくれと、そばにいてくれと、望んでもいいのか」
気がついたら、メオラも両腕を持ち上げてラシェルの背中に回していた。
「わたしは……あまり力になれないかもしれないけれど、……でも、それでも、あなたが必要とするなら」
ここにいるわ。
そう言った声はほとんどかすれて消えそうだった。
この先も共にあるとして、それは簡単なことではないと、メオラもラシェルもわかっている。
なにしろラシェル自身が下賤の女の腹から生まれた王子だ。
ラシェルの血筋だけで王位継承を認めたがらない輩もいる。
ラシェルがメオラをそばに置こうものなら、親が親なら子も子だと揶揄されることは目に見えている。
だからこそお互いに、好きだとも愛しているとも言わない――言えない。