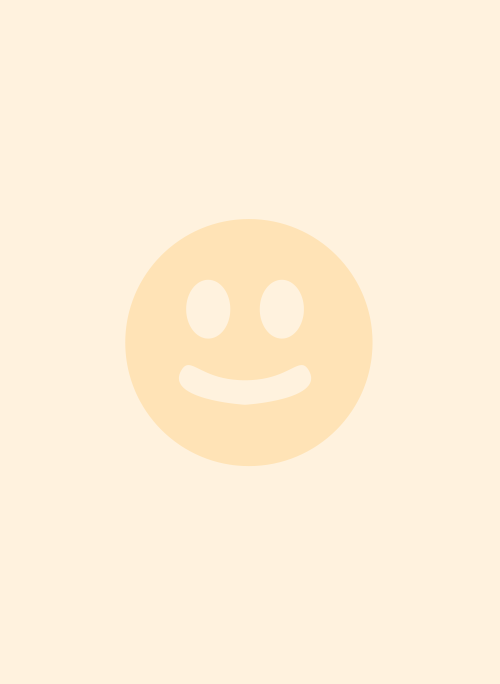「それを肌身離さず、首につけておきなさい。
風呂の時でもです」
「これをつけてれば、再発は免れるんですか?」
「いいえ、鬼の本能の力は、たかが人の技術では滅殺できません」
あっさりと否定され、酒童は落胆する。
「けれども、鬼の血に抵抗する呪力が、それには込められています」
「と、いいますと」
「抗ガン剤のようなものですよ。
本能による暴走を最小限に抑えるのです。
その人間の意識が鬼の本能に支配されないように。
まあ……退魔の呪物なだけあって、もれなく魔物に苦痛を与える副作用がついてきますが」
鬼になる確率は低くなる。
その代わりに、鬼の血と呪法による力のぶつかり合いで、自分の体に激痛が走るだろう。
鬼門はそう言いたかったのだ。
「大丈夫です、耐えるくらいなら」
「本当に?」
酒童をぎろりと睨みつけ、鬼門は太い声で追求した。
「たとえ死ぬほどの激痛に襲われたとしても、いっそ楽になれと内なる自分が囁きかけたとしても。
あなたは、鬼に呑まれない自信と精神力がありますか?」
問われて、酒童は人狼と一戦を交えた夜を想起する。
そういえばあの時誰かに囁かれた。
子供の声。
それが自分に、鬼になれと促した。
そして自分は、それにやすやすと流された……。
「―――」
首を垂れる酒童に、さらに鬼門は、矢継ぎ早に忠告した。
「この首飾りの効力は、完全に再発を阻止できるというわけではありません。
たった数分の苦痛に耐えきれず、少しでも楽になろうと鬼に成り果てたもの。
それで人を殺しかけた者も多くいます」
「社会問題には、ならなかったんですか」
「揉み消される、というやつです」
呼吸をするように、鬼門は衝撃の真実を述べていく。
酒童には一瞬、鬼門の右眼が冷酷に光を消したように見えた。
「じゃあ、俺の心次第では……」
「鬼になるのもあり得るということです。
……あなたにとっての、大切な人々の生殺与奪権は、あなたが握っているも同然なのですよ」
気を抜けば、一瞬で周りの人を殺してしまうと思え。
鬼門の忠告の主旨は、それなのだ。
酒童は青ざめる。
青ざめてから、うまく息が吸えないのを感じる。
「……わかりました」
酒童は力強く言ってみせた。
手の内に食い込む爪は、もう長く伸びてはいなかった。