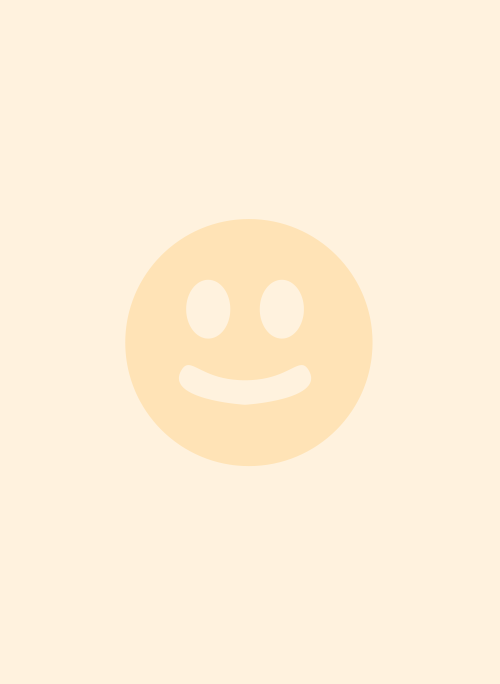「おかえりなさい」
とろん、と目尻を垂らし、陽頼は絵草紙に出る女人のように伸ばされた髪を、耳にかけた。
(昨日の残り、あっためなきゃ)
昨日の残り、とは、夕飯のことである。
陽頼は、いつも夕飯をひとりで食べる割には、必ず2人分はある量の料理を作る。
だから絶対に、翌日の朝食の分は残るのだ。
崩していた足を立てて、台所へと向かおうとする陽頼の腕を、不意に酒童の手が掴んだ。
「ひゃっ……」
ぐいと腕を引かれて、陽頼は勢いで布団に倒れこんだ。
そんな陽頼の華奢な身体を、絹をたぐるように酒童が引き寄せる。
眠っていたはずの酒童は、ばっちりと目を覚ましていた。
「起きてたの?」
状況がよく飲み込めず、陽頼は間の抜けた顔で訊いた。
「さっき起きたんだよ、横でがさがさ音がするから」
酒童は、まだ若干眠気が残っているのか、鋭敏な容姿には似合わない、のっそりとした口調で言った。
そして、いうやいなや、酒童はなにを思ったのか、陽頼を腕に収めて抱き締めた。