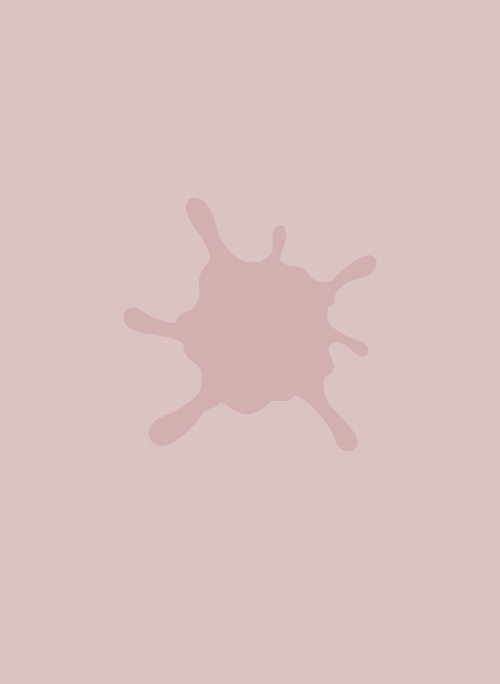『ちょっと待ってな。』
そう言うと、緑は奥の方へと消えていった。
だだっ広い豪邸にたった独り、という、とてつもない恐怖と孤独感が僕を襲う。
紅い絨毯の敷かれた廊下は、ぼんやりと薄暗い明かりしかついておらず、僕は益々 怖くなった。
部屋へ引き返した僕は、両膝を抱えて部屋の隅で震えていた。
『緑!緑…!
早く戻ってきて…!』
膝におでこをつけ、声を抑えて小さく叫ぶ。
すると、甘いココアの匂いがふわり、香ってきた。
『白夜。』
甘い声が僕を呼ぶ。
『緑っ…!』
もう身寄りの無い僕は、自分が感じているよりも数段 孤独に敏感になっていた。
人の体温を感じたかった。
2つの湯気の立つカップを持つ緑に、僕は飛び付いた。