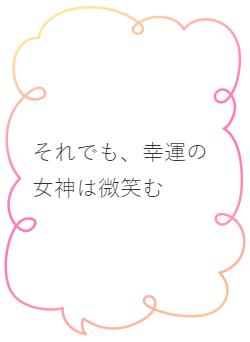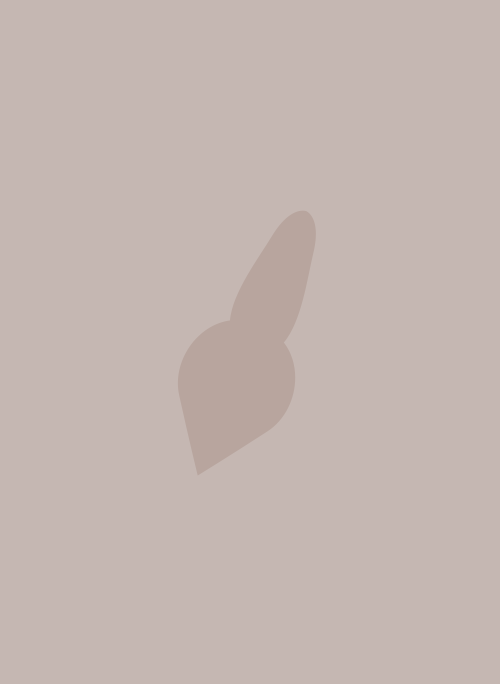―――じゃあね。
そう言ったときの、壊れそうな青菜が、忘れられない。
翌日、不敵に彼女は笑ったけれど・・・・・・それでも、心に残る。
一瞬でも、あんな顔をさせてしまった自分が、悔しくて悔しくて堪らない。
そんな状況に追い込んだコイツらを、許す事なんて、できない。
俺の言葉に、彼らはグッと唇を噛み締めた。
「分かってる・・・・・青菜の親だなんて、助けたいだなんて、言う資格などないことなど・・・・・・・・・。」
敦さんが、悔しそうに、無念そうに呟く。
「何も・・・・・・・・・・」
海さんが、震える声で呟いた。
「何も、してあげられなかった・・・・・・」
目に、涙をため、吐き捨てるように彼女は言う。
「私は・・・・・何もっ!!!!!」
握り締められた拳から―――
「!!!??」
「なっ―――海っ!?」
りおさんが叫んだ。
そう言ったときの、壊れそうな青菜が、忘れられない。
翌日、不敵に彼女は笑ったけれど・・・・・・それでも、心に残る。
一瞬でも、あんな顔をさせてしまった自分が、悔しくて悔しくて堪らない。
そんな状況に追い込んだコイツらを、許す事なんて、できない。
俺の言葉に、彼らはグッと唇を噛み締めた。
「分かってる・・・・・青菜の親だなんて、助けたいだなんて、言う資格などないことなど・・・・・・・・・。」
敦さんが、悔しそうに、無念そうに呟く。
「何も・・・・・・・・・・」
海さんが、震える声で呟いた。
「何も、してあげられなかった・・・・・・」
目に、涙をため、吐き捨てるように彼女は言う。
「私は・・・・・何もっ!!!!!」
握り締められた拳から―――
「!!!??」
「なっ―――海っ!?」
りおさんが叫んだ。