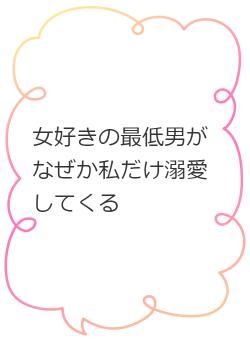なのに、今は私1人でここにいる。
優輝さんにキスされた唇は、何度拭ってみてもその感覚は消えてくれない。
きっと、罪悪感として、一生私の体にしみついてしまうんだろう。
「もう、帰りたいよぉ…」
小さく呟いて、ペガサスに寄り掛かる。
ペガサスはヒンヤリと冷たくて、煮詰まっている私の体をほどよく冷やしてくれた。
優輝さんにキスされた唇は、何度拭ってみてもその感覚は消えてくれない。
きっと、罪悪感として、一生私の体にしみついてしまうんだろう。
「もう、帰りたいよぉ…」
小さく呟いて、ペガサスに寄り掛かる。
ペガサスはヒンヤリと冷たくて、煮詰まっている私の体をほどよく冷やしてくれた。