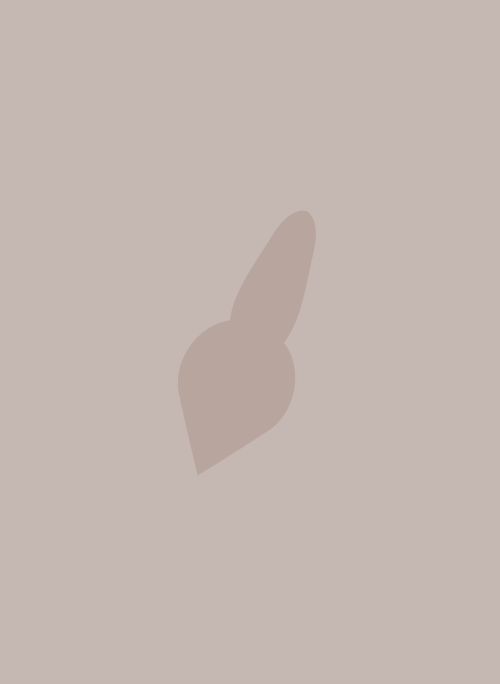「わかった」
私は、『行かないで』と言いそうになる口を必死に塞いで、二人を見送った。
二人は小さく小さくなっていき、やがて見えなくなった。
「泣きたいのは こっちだよ」
私は小さく呟くと、急いで次の教室へ向かった。
部屋に入ると同時に、授業開始のチャイムが鳴り響いた。
「おい佐々本、遅いぞ」
「すいません」
私は、『行かないで』と言いそうになる口を必死に塞いで、二人を見送った。
二人は小さく小さくなっていき、やがて見えなくなった。
「泣きたいのは こっちだよ」
私は小さく呟くと、急いで次の教室へ向かった。
部屋に入ると同時に、授業開始のチャイムが鳴り響いた。
「おい佐々本、遅いぞ」
「すいません」