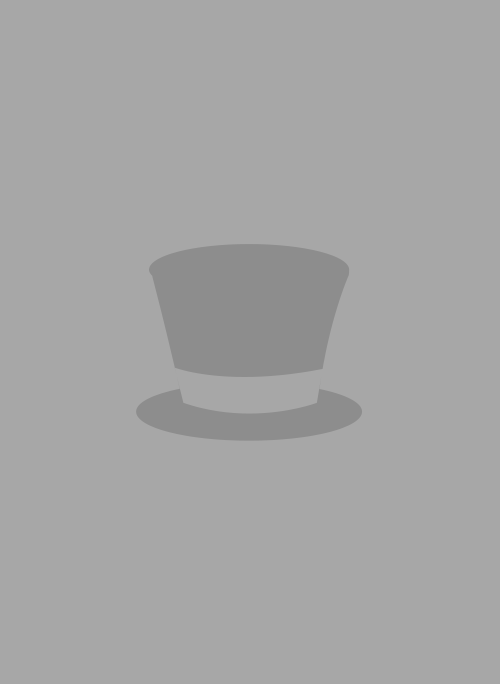普通ならその得体の知れないものに乗っ取られてしまうのでは、と恐怖を感じるところなのかもしれないが、不思議とそれはなかった。
きっと、それがとても優しいものであるということが共にある私にはわかっているからだと思う。
それに、なぜかとても懐かしい気持ちにもなる。
そして、自分自身をどこか遠くから見ているように、とても客観的に物事が進み始めた。
目を開けると、舞台の上でリュウとスサノオが座って何か話している姿が目に入ってきた。
スサノオはところどころ怪我をしているようだが、それほど大きな怪我ということはなさそうだった。
一方、リュウはというと私が気を失う前の状態が嘘のように、どこにも傷一つ見当たらなかった。
何故なのか?そんなことはどうでも良くて、ただその事実に私はホッと胸をなでおろした。
そして、私の口が勝手に開かれた。
『スサノオ、案内しなさい』
スサノオは、当たり前のように頷くと前をたって歩き出す。
きっと、それがとても優しいものであるということが共にある私にはわかっているからだと思う。
それに、なぜかとても懐かしい気持ちにもなる。
そして、自分自身をどこか遠くから見ているように、とても客観的に物事が進み始めた。
目を開けると、舞台の上でリュウとスサノオが座って何か話している姿が目に入ってきた。
スサノオはところどころ怪我をしているようだが、それほど大きな怪我ということはなさそうだった。
一方、リュウはというと私が気を失う前の状態が嘘のように、どこにも傷一つ見当たらなかった。
何故なのか?そんなことはどうでも良くて、ただその事実に私はホッと胸をなでおろした。
そして、私の口が勝手に開かれた。
『スサノオ、案内しなさい』
スサノオは、当たり前のように頷くと前をたって歩き出す。