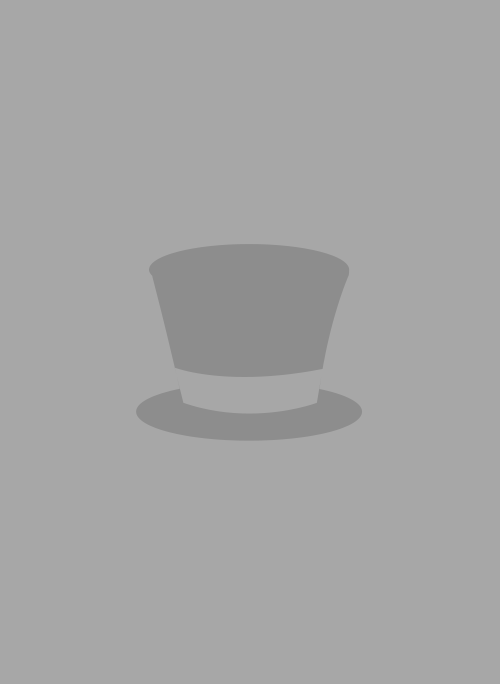どうしても頭に浮かぶのはある少女の姿。
巻き込むわけにはいかないと、理性で反論するのに、本能は彼女を求めていた。
『眩く輝く光』というのが良くわからなかったが、それ以外の言葉は紛れもなく彼女、ハルカを指し示している。
それは、ある意味一種の賭けだったのかもしれない。
普段の自分からは想像できないほど、半ば無理やりにハルカを家まで連れてきていた。
本当は、もっとちゃんと丁寧に説明するつもりだった。
だけど、ハルカを前にすると何故だかいつもの自分が保てなくなる。
ボロを出さないように、ついつい言葉少なになってしまっていたから、ハルカには居心地悪い思いをさせてしまっていたかもしれない。
巻き込むわけにはいかないと、理性で反論するのに、本能は彼女を求めていた。
『眩く輝く光』というのが良くわからなかったが、それ以外の言葉は紛れもなく彼女、ハルカを指し示している。
それは、ある意味一種の賭けだったのかもしれない。
普段の自分からは想像できないほど、半ば無理やりにハルカを家まで連れてきていた。
本当は、もっとちゃんと丁寧に説明するつもりだった。
だけど、ハルカを前にすると何故だかいつもの自分が保てなくなる。
ボロを出さないように、ついつい言葉少なになってしまっていたから、ハルカには居心地悪い思いをさせてしまっていたかもしれない。