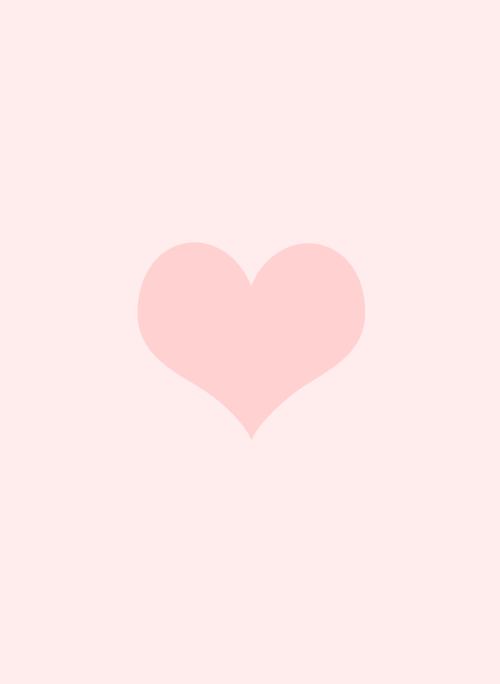鷹野は頬杖をついたまま、つまらなそうに友典を見ている。
「まあ、いいけど。気にしてたみたいだから」
とにかく、2人きりじゃなくなったから、破廉恥な妄想しなくて良いからね、と、くすくす笑った鷹野は。
諦めて再びシャープペンシルを動かし出した雅を、じっと、憐れむように、眺めた。
過呼吸。
目の当たりにしたのは、1度だけ。
花火大会の日に、雷と昌也の赤い髪が引き金だった。
あれは、過呼吸とは違っていた気もする。
柳井に、襲われるも同然に組み敷かれ、キスをされたらしい。
思わず、手が伸びた。
編み込んだはずの髪が、すっかり解け、うねりを浮かべたまま、無造作に結ばれている。
キスを、しても大丈夫だろうか。
額に、頬に、唇に。
今すぐに。
きっと、まだ怖がる。
可哀想に。
抵抗はしていなかった、と言いにくそうに呟いた友典の言葉が、脳裏をよぎった。
凱司は怒るだろう。
雅はその時、知り合う以前のように、“諦めた”のだろうから。