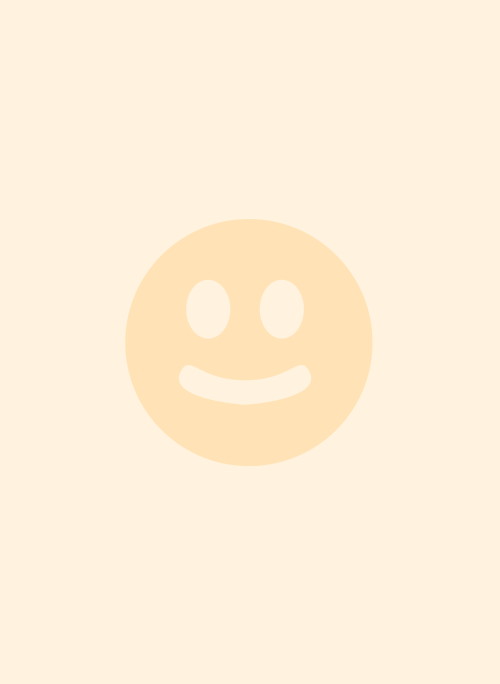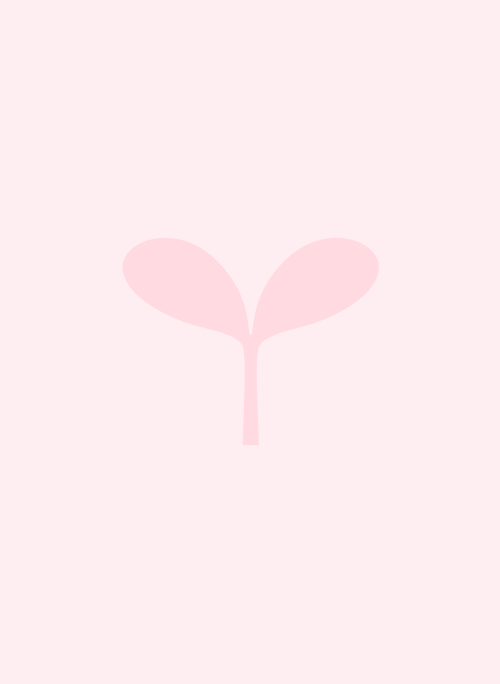その日はちょうど高校最後の夏期補修授業がはじまった日で、
ひどく蒸し暑い日だった。
午後、母さんからのメールを見たボクは、
すぐさま職員室へと向かいことの展開を伝えに行った。
「今日、祖父が他界する予定です。」
担任の笠井は予想に反し眉間にものすごいしわを寄せ、
睨みつけるような目でボクを見た。
正直、そんな顔されても困る。
残念ながらボクは明日から学校を休む理由に
これ以上の言葉は持ち合わせていない。
気温三十二度。
職員室の古臭い業務用のクーラーは鼻息のような轟音を放ち、
彼の机の上にある午後2時を指した時計は彼の眉と同じ形をしながら黙々と時を刻んでいる。
カチッカチッっと、冷たい沈黙の音が聞こえるようで
目の前にいる担任に顔をのぞかれながらボクは必死に視線をずらしていた。
約一年前、祖父は癌だと告知された。
直接、医師の話を聞いたわけじゃないから
詳しくは分からないけど、一緒に話を聞いていた母さんによるとこのときすでに、
肺、肝臓、食道、胃そしてすい臓と
身体中のあちらこちらにいたるまで転移していたらしい。
はじめて、耳にした近い身内が死ぬという現実。
ただ、このときのボクは死というものをまるで理解しておらず、
ただ、単純に
「もうすぐ死ぬらしい。」
なんてあっけらかんと受け答えしていた。
いや、本当は死ぬってことが信じれなくて
そのうちに
「治るだろう」
ってどこか根拠のない自信で満たされていただけかもしれない。
ひどく蒸し暑い日だった。
午後、母さんからのメールを見たボクは、
すぐさま職員室へと向かいことの展開を伝えに行った。
「今日、祖父が他界する予定です。」
担任の笠井は予想に反し眉間にものすごいしわを寄せ、
睨みつけるような目でボクを見た。
正直、そんな顔されても困る。
残念ながらボクは明日から学校を休む理由に
これ以上の言葉は持ち合わせていない。
気温三十二度。
職員室の古臭い業務用のクーラーは鼻息のような轟音を放ち、
彼の机の上にある午後2時を指した時計は彼の眉と同じ形をしながら黙々と時を刻んでいる。
カチッカチッっと、冷たい沈黙の音が聞こえるようで
目の前にいる担任に顔をのぞかれながらボクは必死に視線をずらしていた。
約一年前、祖父は癌だと告知された。
直接、医師の話を聞いたわけじゃないから
詳しくは分からないけど、一緒に話を聞いていた母さんによるとこのときすでに、
肺、肝臓、食道、胃そしてすい臓と
身体中のあちらこちらにいたるまで転移していたらしい。
はじめて、耳にした近い身内が死ぬという現実。
ただ、このときのボクは死というものをまるで理解しておらず、
ただ、単純に
「もうすぐ死ぬらしい。」
なんてあっけらかんと受け答えしていた。
いや、本当は死ぬってことが信じれなくて
そのうちに
「治るだろう」
ってどこか根拠のない自信で満たされていただけかもしれない。