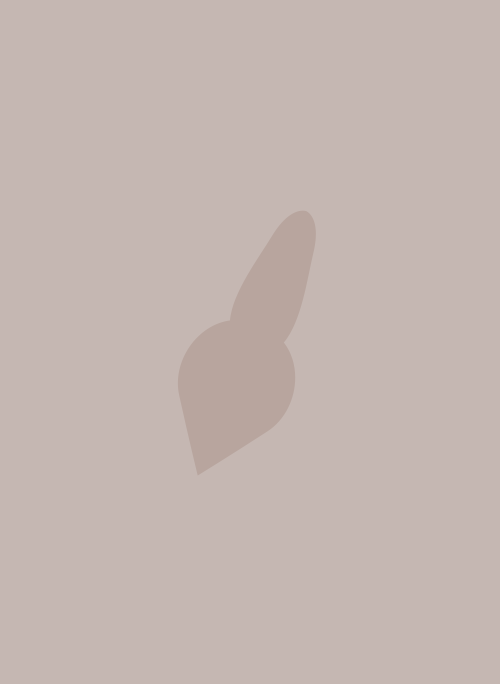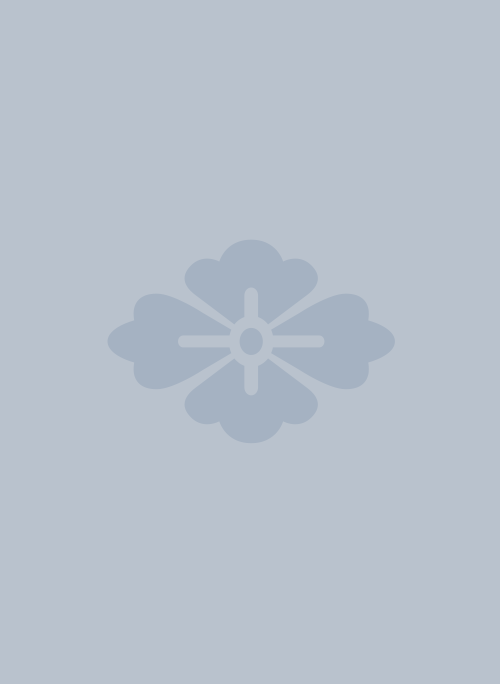一五九四「冬の雨よ、たえまなく降らないでくれ。紅の充満した山が散ってしまうのが惜しまれるから」 2011.0920
・光明皇后の宮での維摩講の時に仏前唱歌(しょうが)された歌。祖父・鎌足の七十回忌といわれる。天候が詠まれていると言うことは当日つくられたか。
一六〇六「」額田王
・四八八に重出。
一六〇七「」鏡王女
・四八九に重出。
一六一〇「高円の秋の野の上にあるナデシコの花。うら若いので(思い)人が刺してくれたナデシコの花」丹生女王 2011.1208
・大宰時代の大伴旅人に贈った歌。「うら若み」が訳しづらい。遠方への左遷と心理状態、寄り添いたいと思う気持ち。
一六二一「私のウチの萩の花が咲いたよ。見にいらっしゃい今から2日くらいしたら散ってしまうでしょうから」巫部麻蘇娘子(かむなぎべのまそおとめ) 2011.0929
・巫部麻蘇娘子は七〇三、一五六二にも見える。家持との相聞歌がある。特殊な姓だが、当時、職能と結びつくか?
一六二七「私の家の返り咲きのフジが、いとおしくて今も見ていました。貴女の笑顔を重ねて」大伴家持 2011.0624
・お中元にちなんで万葉の贈答。紀女郎の七四二、額田王の一一三、藤原広嗣の一四五六を併せて紹介。植物に和歌をよじり季節感を共有する。鮒鮓の中の密書。
・光明皇后の宮での維摩講の時に仏前唱歌(しょうが)された歌。祖父・鎌足の七十回忌といわれる。天候が詠まれていると言うことは当日つくられたか。
一六〇六「」額田王
・四八八に重出。
一六〇七「」鏡王女
・四八九に重出。
一六一〇「高円の秋の野の上にあるナデシコの花。うら若いので(思い)人が刺してくれたナデシコの花」丹生女王 2011.1208
・大宰時代の大伴旅人に贈った歌。「うら若み」が訳しづらい。遠方への左遷と心理状態、寄り添いたいと思う気持ち。
一六二一「私のウチの萩の花が咲いたよ。見にいらっしゃい今から2日くらいしたら散ってしまうでしょうから」巫部麻蘇娘子(かむなぎべのまそおとめ) 2011.0929
・巫部麻蘇娘子は七〇三、一五六二にも見える。家持との相聞歌がある。特殊な姓だが、当時、職能と結びつくか?
一六二七「私の家の返り咲きのフジが、いとおしくて今も見ていました。貴女の笑顔を重ねて」大伴家持 2011.0624
・お中元にちなんで万葉の贈答。紀女郎の七四二、額田王の一一三、藤原広嗣の一四五六を併せて紹介。植物に和歌をよじり季節感を共有する。鮒鮓の中の密書。