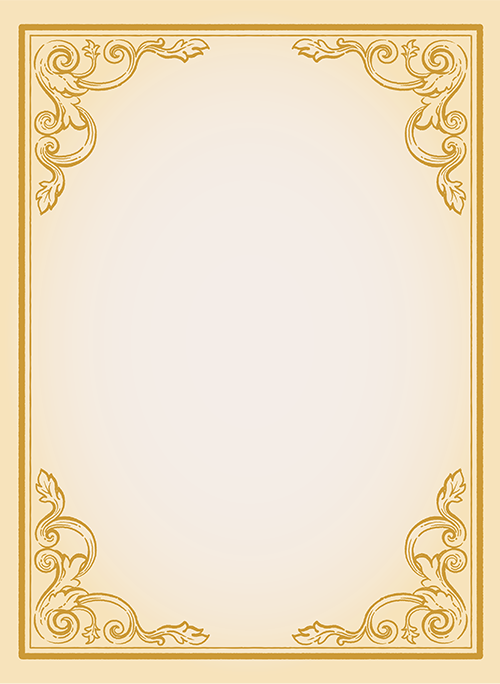昼食後に行われるいつもの退屈な会議。マネージャーと言う立場になってしまった以上、こういった会議にも出席する機会が増えた。昇格するのも良し悪しだなと溜息を吐いたのも束の間、会議室の窓辺に差し込んだ春の穏やかな日差しをポカポカと浴びながら、勝手に落ちてくる瞼と必死に戦っていた。
リハーサルを見に行ったその日から、叶子は足繁(あししげ)く彼の家へと通っていた。日を追う毎に増えていくダンボールを見ては、彼の居ない毎日を想像すると勝手に涙が込み上げてくる。
そんな叶子を、ジャックは何も言わず抱き締めてくれた。
明後日になると、ジャックは一足先にアメリカへと旅立ってしまう。
しばらく会えなくなると思うと、一日、一時間でも多く彼との時間を記憶に留めておきたかった。
「――っ」
意識を手放しかけた時、ジャケットが小刻みに震えるのを感じた。ポケットから携帯電話を取り出した叶子は、液晶画面に映し出された名前を見て一気に目が冴えた。
慌てて会議室を飛び出し、すぐに受話ボタンを押す。ざわついた音が電話の向こうから聞こえた事で、外から掛けて来ているのだとすぐに判った。
「もしもし?」
「あぁ、そう。それ、うん……。──あれ? もしもし?」
「はいはい?」
「ああ、ごめんごめん。今大丈夫?」
「今会議中なんだけど。どうしたの?」
「あー、そうだったんだ。ごめんね、用件だけ言わせて。実は今日、今からアメリカに急遽発つ事になったんだ」
「えっ!? 嘘でしょ?」
「いや本当。今朝急に決まってチケットの手配やら荷物の準備やらでバタついちゃってさ、電話するのが遅れちゃったよ。ごめんね」
どうりで周囲が騒がしいはずだ。ジャックのその言葉により、今まさに空港に居るのだという事がわかった。
「遅すぎるよ! 今からなんて……見送りに行けないじゃない!」
「はは、いいよ見送りなんて。悲しくなるから」
「貴方が良くても私が嫌なの! ちゃんとさよならを言いたいのに!」
「やっぱり来て貰わなくて良かったよ。『さよなら』なんて言われたくないもの」
「そういう、――意味じゃなくて」
急にしんみりとなり、お互い会話が途切れてしまう。言葉が無くなった事で、電話口にアメリカ行きのフライトを知らせる放送が聞こえた。
「あ、もう行かなきゃ」
「……」
「――カナ、いいかい? 離れていても僕はいつも君の事を想ってる。大丈夫、僕達はきっと上手くやれるさ」
「……う、ん」
突然過ぎる別れの言葉に、叶子は返す言葉が見つからない。こんな時こそもっと気の利いた言葉を言えればいいが、ボキャブラリーが貧困過ぎて何も思い浮かばなかった。
「向こうに着いたら電話する。──カナ?」
「なに?」
「──愛してるよ」
「うん、私も……愛して――ます」
「ふふっ、かわいいなぁ」
「は、恥ずかしい」
「じゃあ、後でね」
「うん、気をつけていってらっしゃい」
「……」
「……」
「電話、切ってよ」
「え? 貴方が切ってよ」
「それが出来ないから言ってるのに!」
「私だって!」
「──お願い、君から切って」
「……判った。じゃあ必ず電話頂戴ね」
「うん」
震える指でボタンを押し、携帯電話を胸に押し当てる。
彼の言葉を思い出しては『大丈夫、私達なら大丈夫』だと心の中で何度も呟き、いつか来るジャックとの再会に思いを馳せた。
リハーサルを見に行ったその日から、叶子は足繁(あししげ)く彼の家へと通っていた。日を追う毎に増えていくダンボールを見ては、彼の居ない毎日を想像すると勝手に涙が込み上げてくる。
そんな叶子を、ジャックは何も言わず抱き締めてくれた。
明後日になると、ジャックは一足先にアメリカへと旅立ってしまう。
しばらく会えなくなると思うと、一日、一時間でも多く彼との時間を記憶に留めておきたかった。
「――っ」
意識を手放しかけた時、ジャケットが小刻みに震えるのを感じた。ポケットから携帯電話を取り出した叶子は、液晶画面に映し出された名前を見て一気に目が冴えた。
慌てて会議室を飛び出し、すぐに受話ボタンを押す。ざわついた音が電話の向こうから聞こえた事で、外から掛けて来ているのだとすぐに判った。
「もしもし?」
「あぁ、そう。それ、うん……。──あれ? もしもし?」
「はいはい?」
「ああ、ごめんごめん。今大丈夫?」
「今会議中なんだけど。どうしたの?」
「あー、そうだったんだ。ごめんね、用件だけ言わせて。実は今日、今からアメリカに急遽発つ事になったんだ」
「えっ!? 嘘でしょ?」
「いや本当。今朝急に決まってチケットの手配やら荷物の準備やらでバタついちゃってさ、電話するのが遅れちゃったよ。ごめんね」
どうりで周囲が騒がしいはずだ。ジャックのその言葉により、今まさに空港に居るのだという事がわかった。
「遅すぎるよ! 今からなんて……見送りに行けないじゃない!」
「はは、いいよ見送りなんて。悲しくなるから」
「貴方が良くても私が嫌なの! ちゃんとさよならを言いたいのに!」
「やっぱり来て貰わなくて良かったよ。『さよなら』なんて言われたくないもの」
「そういう、――意味じゃなくて」
急にしんみりとなり、お互い会話が途切れてしまう。言葉が無くなった事で、電話口にアメリカ行きのフライトを知らせる放送が聞こえた。
「あ、もう行かなきゃ」
「……」
「――カナ、いいかい? 離れていても僕はいつも君の事を想ってる。大丈夫、僕達はきっと上手くやれるさ」
「……う、ん」
突然過ぎる別れの言葉に、叶子は返す言葉が見つからない。こんな時こそもっと気の利いた言葉を言えればいいが、ボキャブラリーが貧困過ぎて何も思い浮かばなかった。
「向こうに着いたら電話する。──カナ?」
「なに?」
「──愛してるよ」
「うん、私も……愛して――ます」
「ふふっ、かわいいなぁ」
「は、恥ずかしい」
「じゃあ、後でね」
「うん、気をつけていってらっしゃい」
「……」
「……」
「電話、切ってよ」
「え? 貴方が切ってよ」
「それが出来ないから言ってるのに!」
「私だって!」
「──お願い、君から切って」
「……判った。じゃあ必ず電話頂戴ね」
「うん」
震える指でボタンを押し、携帯電話を胸に押し当てる。
彼の言葉を思い出しては『大丈夫、私達なら大丈夫』だと心の中で何度も呟き、いつか来るジャックとの再会に思いを馳せた。