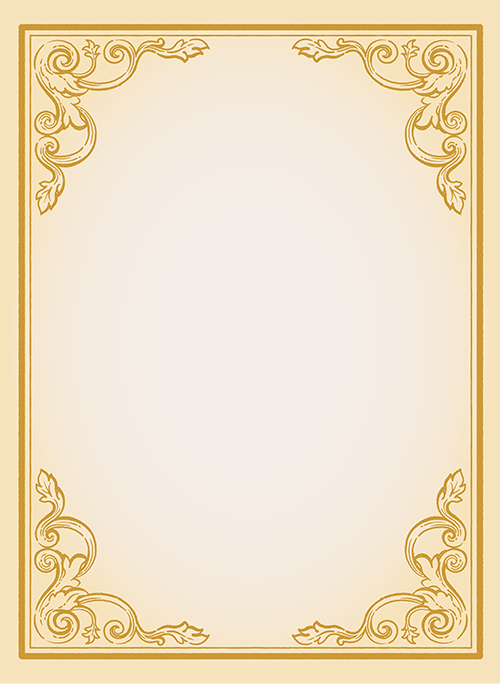朝からけたたましく電話が鳴り響いているオフィスで、もらった名刺を取り出し昨晩の出来事を思い出していた。以前貰ったものと同じく社名と名前だけで特に肩書きは記されていなかったが、彼の立ち振る舞いや高級ホテルでの顔の広さから推測して、違う世界にいる人間なんだろうと思ったと同時に、自分には絶対手の届かない人だということは言葉にするまでもなく理解しているつもりだった。なのに、頭の中は気付けば彼の事で一杯になってしまう。やさしい眼差しで微笑みかけ、穏やかな口調で語りかける。叶子の手をすっぽりと包んでしまうほど大きな彼の手は、男性とは思えないほど柔らかく、そして温もりを感じた。
(素敵な人だなぁ)
心ここに在らずな叶子の手から彼の名刺が取り上げられ、やっと我に返った。
「何これ?」
「ちょっと、藍子! 返してよ!」
よりによって一番見られたくない相手に見られてしまった。急いで名刺を奪い返すと二度と取られまいとすぐにバッグの中へと仕舞い込んだ。
「──あんた、その人と知り合いなの?」
「え?」
さも、彼の事を知っているかのような藍子の口調に、ゴクリと息を呑む。藍子は叶子のマウスをおもむろに掴むとパチパチとキーボードを弾き、何やら検索を始めた。
彼の会社名を検索窓に打ち込んでいくのをただひたすら息を呑んで見つめている。エンターキーが押されたと同時に彼の会社名が画面一杯に表示され、藍子はその中の一つを選択した。
「やっぱり。ほら、その名刺の人ってこの人でしょ?」
食い入る様に画面を覗き込むと、そこには彼の画像と会社の詳細が事細かく書いてあった。驚いた表情で画面を見つめている叶子を見て、藍子は返事を聞かずともこの人物と名刺に記された人物が同一人物だと判った。
「あんた凄いじゃん。こんな大物とどうやって知り合ったの?」
「どうやって、……って」
「ね、ね、この人とどういう関係? ……もしかして付き合ってたりすんの?」
デスクに両手をついて叶子の顔を覗き込みながら、小さな声で聞いてくる藍子の表情は、言うまでも無く興味深々な様子だった。
「そ、そんなわけないでしょ!た、たまたま取引先で会って・・・ご挨拶しただけだよ。」
藍子に話してしまえば、あっと言う間に社内に広まるのが目に見えている。それだけは避けたいと思った叶子は体のいい嘘を吐く事で逃れようと試みるが、目を泳がせながら吐いた嘘は、藍子に更なる興味を与えただけだった。
「ふ~ん……」
藍子はデスクについていた手を離すと、腕を組み怪訝そうな顔で彼女を見下ろしている。早くこの話を終わらせる為に別の画面を開いて又仕事に取り掛かったが、藍子はまだ叶子の側から移動する様子は無かった。
「あのさ、」
思わずピクッと肩がすくみ恐る恐る顔を向けた。と、同時に、遠くから藍子を呼ぶ声が聞こえてきて、竦んだ肩を一気に脱力させた。
「ほ、ほら、呼んでるよ?」
「……はーい、何ですか?」
藍子は何か言いたげに横目で叶子を睨みつけると、呼ばれた方へと去っていった。
「ふぅ。危なかった……」
藍子が立ち去ったのを確認した後、こっそり先程の画面をもう一度見返した。プロフィール欄は“不明”と記載されているものが殆どではあったが、少なくとも叶子がまだ知る事の無い彼が沢山あった。
「……。」
(これじゃ藍子の事を“ゴシップ好き”だなんて、私が言えないや)
自分のしている事が、余所様の家をこっそりのぞき見しているような気がして恥ずかしくなる。スクロールする指を止めると画面を閉じて再び仕事に戻った。
(会いたいなぁ)
叶子の胸の奥では既にそんな感情で溢れかえっていた。
◇◆◇
「…… …… です。以上で本日の業務は終了となります」
真っ暗なオフィスの扉を両手で開け放ち、ソファーに上着と書類を無造作に投げ捨てた。首に絞まるものを片手で緩めると、少し疲れた表情で秘書のジュディスに労(ねぎら)いの言葉を述べた
「はい、お疲れ様。遅くまで悪かったね」
そう言いながら振り返った瞬間、ジュディスは肩をすくめ両手に抱えた彼の鞄をきつく握り締めた。
「お、お疲れ様でした! ……お荷物こちらに置かせて頂きます」
心なしかジュディスの頬が朱に染まった様に見える。と思った途端、それを悟られたくないとでも思ったのか、彼女は逃げるようにして、扉へ向かった。
「……あ、明日私はお休みを頂きます」
「――となると明日はカレンかな?」
「はい そうです」
「了解。ゆっくり休んでね」
ジュディスは深くお辞儀をすると、静かに扉を閉めた。
ソファーに腰を落としテーブルの上に両足を組んでのせる。デスクに置いてある時計に目をやると時は既に“今日”が終わりを告げ“明日”に変わっているのを知った。
仕事をして居る時は全く気にならないが、一段落ついた時に必ずと言っていいほど、デスクの上にある電話に自然と目が行ってしまう。
(あれから1週間かぁ)
シャツの胸ポケットから携帯を取り出し、着信履歴をチェックした。
「嫌われちゃったかなぁ……」
パタンと片手で携帯電話を折りたたむと、そのままポンッと向かいのソファーに放り投げた。頭の下で両手を組みながら身体を横たえると、あの日の事が自然と頭の中を過ぎる。
辛いものが苦手な事。
笑い上戸で感情移入が凄まじく、まるで自分の事の様に一喜一憂してくれる事。
───そして、……彼女に触れた事。
彼女に触れた手を見つめると、彼女の笑顔が目の前に浮かんでは消えを繰り返し、幻想の彼女を捕まえたくなり手を軽く握りしめた。
「はぁ~失敗しちゃったなぁ~。……待ってらん無いよ」
あの日、電話番号を聞かなかった事をジャックは今更ながらに激しく後悔した。
「――会いたいよ」
一言そう呟いてゆっくり目を閉じると、いつの間にか自分の頭の中が彼女で一杯になっている事に気付き思わず笑みが零れ落ちた。
(素敵な人だなぁ)
心ここに在らずな叶子の手から彼の名刺が取り上げられ、やっと我に返った。
「何これ?」
「ちょっと、藍子! 返してよ!」
よりによって一番見られたくない相手に見られてしまった。急いで名刺を奪い返すと二度と取られまいとすぐにバッグの中へと仕舞い込んだ。
「──あんた、その人と知り合いなの?」
「え?」
さも、彼の事を知っているかのような藍子の口調に、ゴクリと息を呑む。藍子は叶子のマウスをおもむろに掴むとパチパチとキーボードを弾き、何やら検索を始めた。
彼の会社名を検索窓に打ち込んでいくのをただひたすら息を呑んで見つめている。エンターキーが押されたと同時に彼の会社名が画面一杯に表示され、藍子はその中の一つを選択した。
「やっぱり。ほら、その名刺の人ってこの人でしょ?」
食い入る様に画面を覗き込むと、そこには彼の画像と会社の詳細が事細かく書いてあった。驚いた表情で画面を見つめている叶子を見て、藍子は返事を聞かずともこの人物と名刺に記された人物が同一人物だと判った。
「あんた凄いじゃん。こんな大物とどうやって知り合ったの?」
「どうやって、……って」
「ね、ね、この人とどういう関係? ……もしかして付き合ってたりすんの?」
デスクに両手をついて叶子の顔を覗き込みながら、小さな声で聞いてくる藍子の表情は、言うまでも無く興味深々な様子だった。
「そ、そんなわけないでしょ!た、たまたま取引先で会って・・・ご挨拶しただけだよ。」
藍子に話してしまえば、あっと言う間に社内に広まるのが目に見えている。それだけは避けたいと思った叶子は体のいい嘘を吐く事で逃れようと試みるが、目を泳がせながら吐いた嘘は、藍子に更なる興味を与えただけだった。
「ふ~ん……」
藍子はデスクについていた手を離すと、腕を組み怪訝そうな顔で彼女を見下ろしている。早くこの話を終わらせる為に別の画面を開いて又仕事に取り掛かったが、藍子はまだ叶子の側から移動する様子は無かった。
「あのさ、」
思わずピクッと肩がすくみ恐る恐る顔を向けた。と、同時に、遠くから藍子を呼ぶ声が聞こえてきて、竦んだ肩を一気に脱力させた。
「ほ、ほら、呼んでるよ?」
「……はーい、何ですか?」
藍子は何か言いたげに横目で叶子を睨みつけると、呼ばれた方へと去っていった。
「ふぅ。危なかった……」
藍子が立ち去ったのを確認した後、こっそり先程の画面をもう一度見返した。プロフィール欄は“不明”と記載されているものが殆どではあったが、少なくとも叶子がまだ知る事の無い彼が沢山あった。
「……。」
(これじゃ藍子の事を“ゴシップ好き”だなんて、私が言えないや)
自分のしている事が、余所様の家をこっそりのぞき見しているような気がして恥ずかしくなる。スクロールする指を止めると画面を閉じて再び仕事に戻った。
(会いたいなぁ)
叶子の胸の奥では既にそんな感情で溢れかえっていた。
◇◆◇
「…… …… です。以上で本日の業務は終了となります」
真っ暗なオフィスの扉を両手で開け放ち、ソファーに上着と書類を無造作に投げ捨てた。首に絞まるものを片手で緩めると、少し疲れた表情で秘書のジュディスに労(ねぎら)いの言葉を述べた
「はい、お疲れ様。遅くまで悪かったね」
そう言いながら振り返った瞬間、ジュディスは肩をすくめ両手に抱えた彼の鞄をきつく握り締めた。
「お、お疲れ様でした! ……お荷物こちらに置かせて頂きます」
心なしかジュディスの頬が朱に染まった様に見える。と思った途端、それを悟られたくないとでも思ったのか、彼女は逃げるようにして、扉へ向かった。
「……あ、明日私はお休みを頂きます」
「――となると明日はカレンかな?」
「はい そうです」
「了解。ゆっくり休んでね」
ジュディスは深くお辞儀をすると、静かに扉を閉めた。
ソファーに腰を落としテーブルの上に両足を組んでのせる。デスクに置いてある時計に目をやると時は既に“今日”が終わりを告げ“明日”に変わっているのを知った。
仕事をして居る時は全く気にならないが、一段落ついた時に必ずと言っていいほど、デスクの上にある電話に自然と目が行ってしまう。
(あれから1週間かぁ)
シャツの胸ポケットから携帯を取り出し、着信履歴をチェックした。
「嫌われちゃったかなぁ……」
パタンと片手で携帯電話を折りたたむと、そのままポンッと向かいのソファーに放り投げた。頭の下で両手を組みながら身体を横たえると、あの日の事が自然と頭の中を過ぎる。
辛いものが苦手な事。
笑い上戸で感情移入が凄まじく、まるで自分の事の様に一喜一憂してくれる事。
───そして、……彼女に触れた事。
彼女に触れた手を見つめると、彼女の笑顔が目の前に浮かんでは消えを繰り返し、幻想の彼女を捕まえたくなり手を軽く握りしめた。
「はぁ~失敗しちゃったなぁ~。……待ってらん無いよ」
あの日、電話番号を聞かなかった事をジャックは今更ながらに激しく後悔した。
「――会いたいよ」
一言そう呟いてゆっくり目を閉じると、いつの間にか自分の頭の中が彼女で一杯になっている事に気付き思わず笑みが零れ落ちた。