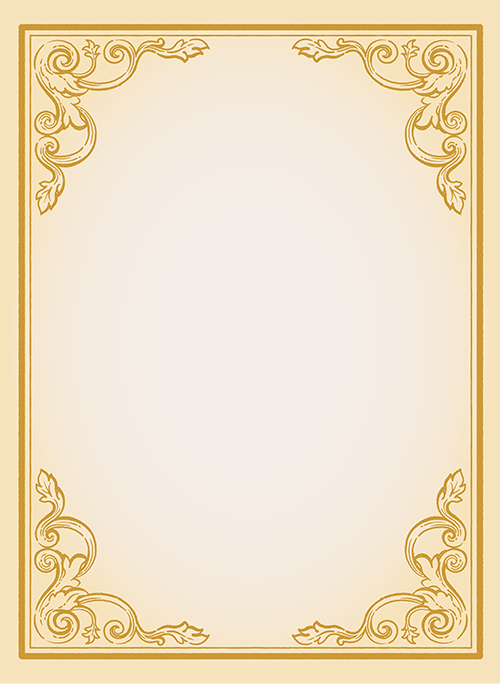暖かく暗い車内。
わずかに感じる揺れが、少し酔った彼女をいとも簡単に眠りの淵へと誘(いざな)う。
──誘惑に負けてはダメ
そう思ったのも束の間、彼女は深い眠りへと落ちていった。
最寄り駅の名前だけ彼に告げると、この間のCDショップで一緒にいた恰幅の良い男性に、彼がそのまま伝えた。
暖かく暗い車内と少しの揺れが、あっという間に彼女の意識を朦朧(もうろう)とさせ、何度も落ちてくる瞼を手で押さえては必死で耐えている。
「眠い? 寝てていいよ、ちゃんと着いたら起こしてあげるから」
肘掛に手をつき顎をのせて窓の外を見ていた彼はそんな彼女の様子に気付くと、まるで母親の様な笑顔でそう言った。しかし、幾らなんでも初めて会う人の横でいきなり眠れるわけがない。眠いのは事実だがこの時間を寝て過ごしてしまうのは、どう考えてももったいないと叶子は思った。
「だ、大丈夫です」
彼に見えないように小さくあくびをして目を赤くして瞳を潤ませながら彼にそう言うと、彼はクスッと笑ってまた外の景色に視線を移した。
車の窓ガラスに映る彼を横目で盗み見しながら、落ちてくる頭を何度も持ち上げる。酔いも手伝ってか頑張り空しく、叶子はあっさりと眠りの地に着いた。
◇◆◇
肩に何かが触れるのを感じて振り向くと、彼女の頭が何度も倒れてきては起き上がるを繰り返している。
(困った人だ)
決して悪い意味ではなく、遊び疲れて眠る無邪気な子供の様な――。と、そんな意を込めてポツリと呟いた。
ジャックはそっと彼女と距離を縮めると、次に彼女の頭が落ちてくる瞬間を狙ってそっと自身の手を彼女の頭に添えた。すると、自然とここが落ち着く場所なんだと理解したかの様に、そのまま彼の肩に頭を埋め膝の上に組んでいた彼女の華奢な手がポトリと解けた。
彼女の髪の香りが鼻につく。
さっきは手を伸ばそうとして慌てて引っ込めたが、今度はなんだか許してもらえるような気がする。──そんな風に思うなんて、もしかすると自分は酔っているのかもしれないと思いつつも、元々我慢すると言う事が苦手な彼はこの衝動を抑えることが出来ず、ゆっくりと指先を伸ばし始めた。
彼女の指先にそっと自分の指を触れさせると、車の揺れにあわせてその指を少しずつ這わせていく。ピクリと彼女の指が動くと彼も又動きを止め、ゆっくりと、決して起こしてしまわないように、そーっと彼女に触れていった。
「……。」
彼の大きくて暖かい手が小さくて華奢な彼女の手にピッタリ重なると、彼は満足気に微笑んだ。
◇◆◇
車の揺れが感じなくなった事で、うっすらと意識が戻ってきた。目の前に現れた景色が見たことの無いものというのはすぐに気付いたが、右手に感じる暖かいものが何なのかを理解するのに少し時間を要した。
頭を上げて横を見ると、ぼんやりした景色の中で自分を見つめている誰かを感じる。やがてその輪郭がはっきりとし、その誰かが彼だという事に気付いた。
「おはよう」
満面の笑みで彼が言った。
「あ、ごめんなさ……、───ぃっ!?」
言いかけて手元へ視線を落とすと、彼の手をしっかりと自分の手が握り締めているのを見て、慌てふためいた。
「あわわ……、ご、ごめんなさい!」
てっきり、寝てる間に自分から握ってしまったんだと勘違いして、慌ててその手を振りほどくと彼は『え?』と言うような表情を浮かべていた。
眠ってしまったのと無意識とはいえ勝手に手を握ってしまったことを思うと恥ずかしくて居ても立っても居られない。 ああ! もうこの世から消えて無くなりたい! と思うほど叶子にとっては耐えられないほどに恥ずかしく、とても破廉恥な出来事に思えた。
そんな叶子と対照的に、彼はきょとんとした表情で彼女を見つめている。やがて彼女が謝った訳を理解したのか、
「ああ。……手?」
その言葉を聞いて又、体がカーッと一気に熱くなった。軽い女だと思われているに違いない。叶子はずっと自分がしてしまった失態を心の中で悔やんでいた。
───そう、次の彼の言葉を聞くまでは。
「これは――、僕が君と手を繋ぎたくなったから、僕から握ったんだよ?」
「……はい?」
(い、今なんておっしゃいました??)
目を丸くして彼を見ると、彼は変わらずニコニコしている。あまりにも反応がない彼女が心配になった彼は困ったなと言う様な顔をした。
「もしかして、迷惑……だった?」
「……、───っ!」
赤い顔をした彼女はやっとコトの事態を理解して、すぐさま頭を左右に激しく振った。
「良かった」
「……。」
ほっとしたような顔で微笑んだ彼を見る度、彼に夢中になっていくのがよく判る。どんどんのめり込んで行く自分がなんだか怖くも感じた。
「あ……っと、そう。もう着いたんだった」
「あっ、」
背筋をピンと伸ばしキョロキョロと車の外を見渡すと、いつもの見慣れた景色が目に入り、今度こそお別れの時間(とき)がやってきたのだと知った。
「今日は本当に、ご馳走になってしまって……。しかも、送って頂いてありがとうございました」
「いえいえ」
彼女が車から降りると、彼もさも当然の様に降りて彼女側に回りこんでくる。彼が何か言いたそうにしているのが判りまだCDと傘を返していない事に気付い叶子は慌ててバッグから取り出した。
「あ、コレ返さなきゃ」
CDを差し出すが、何故か彼は受け取ろうとしない。
「ああ、うーん」
この期に及んで、腕を組みながらしばし何か考えている様子だ。今日の目的はこのCDを返すことだと言うのに、彼は一体何を渋って居るのだろう? 彼女が頭を傾げていると、
「今日は見なかったことにするよ」
「え?」
「又、今度返して」
そう言うと胸ポケットから名刺とペンを出し、スラスラと何か書き出した。それを手渡されて見て見ると、そこには彼の携帯番号らしきものが書かれていた。
「───もし良かったら、電話してくれるかな?」
───ま、また会えるんだ!
そう思うと冬の寒さなんてどこかに行ってしまった様に、ポカポカと体が暖かくなってきて嬉しさで溶けてしまいそうになる。
「……は、い」
「じゃ、待ってるから」
───おやすみ。
そう言うと、黒塗りの高級車に乗り込みその車は静かに動き出した。窓を下げ、彼が中から手を上げているのに応えるように、彼女も小さく手を上げる。彼女は彼の車のテールランプの明かりが見えなくなるまで、その場を動く事が出来なかった。
わずかに感じる揺れが、少し酔った彼女をいとも簡単に眠りの淵へと誘(いざな)う。
──誘惑に負けてはダメ
そう思ったのも束の間、彼女は深い眠りへと落ちていった。
最寄り駅の名前だけ彼に告げると、この間のCDショップで一緒にいた恰幅の良い男性に、彼がそのまま伝えた。
暖かく暗い車内と少しの揺れが、あっという間に彼女の意識を朦朧(もうろう)とさせ、何度も落ちてくる瞼を手で押さえては必死で耐えている。
「眠い? 寝てていいよ、ちゃんと着いたら起こしてあげるから」
肘掛に手をつき顎をのせて窓の外を見ていた彼はそんな彼女の様子に気付くと、まるで母親の様な笑顔でそう言った。しかし、幾らなんでも初めて会う人の横でいきなり眠れるわけがない。眠いのは事実だがこの時間を寝て過ごしてしまうのは、どう考えてももったいないと叶子は思った。
「だ、大丈夫です」
彼に見えないように小さくあくびをして目を赤くして瞳を潤ませながら彼にそう言うと、彼はクスッと笑ってまた外の景色に視線を移した。
車の窓ガラスに映る彼を横目で盗み見しながら、落ちてくる頭を何度も持ち上げる。酔いも手伝ってか頑張り空しく、叶子はあっさりと眠りの地に着いた。
◇◆◇
肩に何かが触れるのを感じて振り向くと、彼女の頭が何度も倒れてきては起き上がるを繰り返している。
(困った人だ)
決して悪い意味ではなく、遊び疲れて眠る無邪気な子供の様な――。と、そんな意を込めてポツリと呟いた。
ジャックはそっと彼女と距離を縮めると、次に彼女の頭が落ちてくる瞬間を狙ってそっと自身の手を彼女の頭に添えた。すると、自然とここが落ち着く場所なんだと理解したかの様に、そのまま彼の肩に頭を埋め膝の上に組んでいた彼女の華奢な手がポトリと解けた。
彼女の髪の香りが鼻につく。
さっきは手を伸ばそうとして慌てて引っ込めたが、今度はなんだか許してもらえるような気がする。──そんな風に思うなんて、もしかすると自分は酔っているのかもしれないと思いつつも、元々我慢すると言う事が苦手な彼はこの衝動を抑えることが出来ず、ゆっくりと指先を伸ばし始めた。
彼女の指先にそっと自分の指を触れさせると、車の揺れにあわせてその指を少しずつ這わせていく。ピクリと彼女の指が動くと彼も又動きを止め、ゆっくりと、決して起こしてしまわないように、そーっと彼女に触れていった。
「……。」
彼の大きくて暖かい手が小さくて華奢な彼女の手にピッタリ重なると、彼は満足気に微笑んだ。
◇◆◇
車の揺れが感じなくなった事で、うっすらと意識が戻ってきた。目の前に現れた景色が見たことの無いものというのはすぐに気付いたが、右手に感じる暖かいものが何なのかを理解するのに少し時間を要した。
頭を上げて横を見ると、ぼんやりした景色の中で自分を見つめている誰かを感じる。やがてその輪郭がはっきりとし、その誰かが彼だという事に気付いた。
「おはよう」
満面の笑みで彼が言った。
「あ、ごめんなさ……、───ぃっ!?」
言いかけて手元へ視線を落とすと、彼の手をしっかりと自分の手が握り締めているのを見て、慌てふためいた。
「あわわ……、ご、ごめんなさい!」
てっきり、寝てる間に自分から握ってしまったんだと勘違いして、慌ててその手を振りほどくと彼は『え?』と言うような表情を浮かべていた。
眠ってしまったのと無意識とはいえ勝手に手を握ってしまったことを思うと恥ずかしくて居ても立っても居られない。 ああ! もうこの世から消えて無くなりたい! と思うほど叶子にとっては耐えられないほどに恥ずかしく、とても破廉恥な出来事に思えた。
そんな叶子と対照的に、彼はきょとんとした表情で彼女を見つめている。やがて彼女が謝った訳を理解したのか、
「ああ。……手?」
その言葉を聞いて又、体がカーッと一気に熱くなった。軽い女だと思われているに違いない。叶子はずっと自分がしてしまった失態を心の中で悔やんでいた。
───そう、次の彼の言葉を聞くまでは。
「これは――、僕が君と手を繋ぎたくなったから、僕から握ったんだよ?」
「……はい?」
(い、今なんておっしゃいました??)
目を丸くして彼を見ると、彼は変わらずニコニコしている。あまりにも反応がない彼女が心配になった彼は困ったなと言う様な顔をした。
「もしかして、迷惑……だった?」
「……、───っ!」
赤い顔をした彼女はやっとコトの事態を理解して、すぐさま頭を左右に激しく振った。
「良かった」
「……。」
ほっとしたような顔で微笑んだ彼を見る度、彼に夢中になっていくのがよく判る。どんどんのめり込んで行く自分がなんだか怖くも感じた。
「あ……っと、そう。もう着いたんだった」
「あっ、」
背筋をピンと伸ばしキョロキョロと車の外を見渡すと、いつもの見慣れた景色が目に入り、今度こそお別れの時間(とき)がやってきたのだと知った。
「今日は本当に、ご馳走になってしまって……。しかも、送って頂いてありがとうございました」
「いえいえ」
彼女が車から降りると、彼もさも当然の様に降りて彼女側に回りこんでくる。彼が何か言いたそうにしているのが判りまだCDと傘を返していない事に気付い叶子は慌ててバッグから取り出した。
「あ、コレ返さなきゃ」
CDを差し出すが、何故か彼は受け取ろうとしない。
「ああ、うーん」
この期に及んで、腕を組みながらしばし何か考えている様子だ。今日の目的はこのCDを返すことだと言うのに、彼は一体何を渋って居るのだろう? 彼女が頭を傾げていると、
「今日は見なかったことにするよ」
「え?」
「又、今度返して」
そう言うと胸ポケットから名刺とペンを出し、スラスラと何か書き出した。それを手渡されて見て見ると、そこには彼の携帯番号らしきものが書かれていた。
「───もし良かったら、電話してくれるかな?」
───ま、また会えるんだ!
そう思うと冬の寒さなんてどこかに行ってしまった様に、ポカポカと体が暖かくなってきて嬉しさで溶けてしまいそうになる。
「……は、い」
「じゃ、待ってるから」
───おやすみ。
そう言うと、黒塗りの高級車に乗り込みその車は静かに動き出した。窓を下げ、彼が中から手を上げているのに応えるように、彼女も小さく手を上げる。彼女は彼の車のテールランプの明かりが見えなくなるまで、その場を動く事が出来なかった。