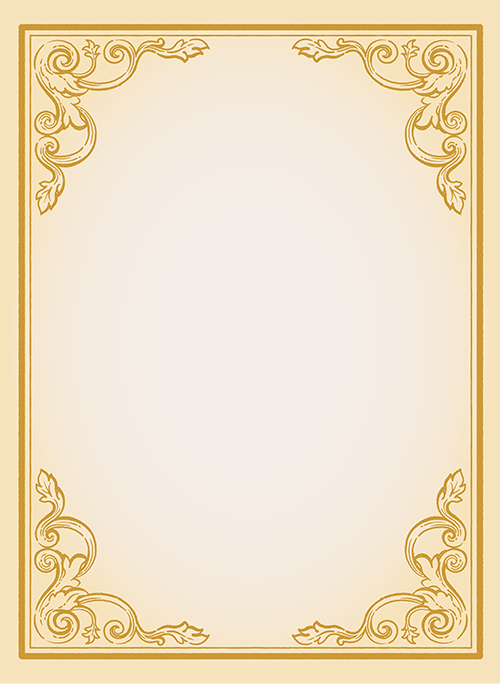楽しい時間はあっという間に過ぎ去り、無情にも別れの時間(とき)を告げる。
店を出たところでお会計をしながらスタッフと談笑している彼を見て、もうこの人と会う事は叶わぬ願いなのだろうかとふと頭をよぎり、気持ちが少し落ち込んだ。
「ありがとう、ご馳走様」
スタッフへの気遣いも忘れず鼻にかけるそぶりなど一切ない彼は、きっとここの上得意であるに違いない。現に、シェフまでもが彼を見送りに出てきて居るのだから。
そのシェフと二言三言言葉を交わした後、叶子の方をチラッと見た。途端、『じゃ』とスタッフ達に手を上げながら、待たせている彼女を気にかけるかのように走りながら戻ってきた。
「ごめん、お待たせ」
彼女は頭を左右に振って答える
「あの、本当にお支払いしなくていいんでしょうか?」
頑(かたく)なに自分が払うと言う方が相手に失礼だと感じ、控えめに尋ねてみた。しかし、返ってきた言葉は思っていた通りで、
「うん、勿論。女性にお金を使わせるなんて、僕のモットーに反するからね」
そう言ってウィンクして見せた。
彼のその口ぶりが今まで数々の女性を虜にしてきたであろう事はいとも簡単に推測でき、それがなんだか微妙な気分にさせられる。
「では、お言葉に甘えて……。有難う御座います」
「どういたしまして」
ニッコリと微笑んだ彼はとても満足している様子だった。
「本当に送らなくていいの?」
正面玄関から出て、冷たい風にあたる。ジャックはコートに袖を通そうとする彼女にさりげなく手を貸した。
「あ、はい、すぐそこなので」
「そっか」
彼女が両手を伸ばしコートの中から長い髪を出した。後ろに立っていたジャックに彼女の髪の香りがふわっと漂った。自然と伸びた手を止め、ジャックは慌てて軽く握りこぶしを作った。
(何、考えてんだ……?)
握りこぶしを見つめて居るところにくるりと振り返った彼女の頬は赤く火照っていて、酔っているのだと誰もが推測できるだろう。本当にこんな状態の彼女を一人で帰らせていいのだろうか、しかし一度断られた手前、又送ると言えばしつこいと思われてしまうのでは無いかと頭を悩ませていた。
どうするかはっきり決め兼ねていると彼女が別れの挨拶を始めてしまい、ジャックは結局言い出すことが出来ずに居た。
「あの、色々とありがとうございました。……じゃあ私はこれで」
深くお辞儀をするとすぐに背中を見せるのは気が引けるのか、ジャックに視線を向けながら駅へと向かう道を歩き出した。見るからに危なっかしい足元に、思わず手が伸びそうになる。
(危なっかしいなぁ。やっぱりしつこいって思われるのを覚悟でもう一回言おうか)
「あのっ……。――!」
側道に駐車していた車のドアが突然開いた事に後ろ向きで歩いている彼女は当然気付かずおぼつく足元で歩き続けた。
「――危ない!」
「え? ……きゃっ! ――。」
考えるのが早いか行動に移すのが早いか。気付けばジャックは彼女の腕を掴み、ぐっと自分の胸元に抱き寄せていた。彼女の体がフワッと彼の胸に吸い込まれ、居場所が判らない彼女の腕は頼りなくただぶら下がって居た。
車中から出てきた人物は彼がじっと睨み続けているのにも気付かず、足早にホテル内に消えていく。その事に思わず“チッ”と舌打ちをした。
ジャックが視線を戻して我に返ると、彼女が腕の中にいる事に気付き慌てて手を離す。
「ああ、っと、ごめん」
「い、いえ、私の方こそ! ボーっとしちゃって」
一歩下がり俯いている彼女は、先ほどより明らかに赤くなった顔をしていた。ポケットに手を突っ込んでいるジャックも又、照れくさそうに鼻を擦った。
「あの……、やっぱり危ないから送らせて?」
彼女は小さく頷いた。
店を出たところでお会計をしながらスタッフと談笑している彼を見て、もうこの人と会う事は叶わぬ願いなのだろうかとふと頭をよぎり、気持ちが少し落ち込んだ。
「ありがとう、ご馳走様」
スタッフへの気遣いも忘れず鼻にかけるそぶりなど一切ない彼は、きっとここの上得意であるに違いない。現に、シェフまでもが彼を見送りに出てきて居るのだから。
そのシェフと二言三言言葉を交わした後、叶子の方をチラッと見た。途端、『じゃ』とスタッフ達に手を上げながら、待たせている彼女を気にかけるかのように走りながら戻ってきた。
「ごめん、お待たせ」
彼女は頭を左右に振って答える
「あの、本当にお支払いしなくていいんでしょうか?」
頑(かたく)なに自分が払うと言う方が相手に失礼だと感じ、控えめに尋ねてみた。しかし、返ってきた言葉は思っていた通りで、
「うん、勿論。女性にお金を使わせるなんて、僕のモットーに反するからね」
そう言ってウィンクして見せた。
彼のその口ぶりが今まで数々の女性を虜にしてきたであろう事はいとも簡単に推測でき、それがなんだか微妙な気分にさせられる。
「では、お言葉に甘えて……。有難う御座います」
「どういたしまして」
ニッコリと微笑んだ彼はとても満足している様子だった。
「本当に送らなくていいの?」
正面玄関から出て、冷たい風にあたる。ジャックはコートに袖を通そうとする彼女にさりげなく手を貸した。
「あ、はい、すぐそこなので」
「そっか」
彼女が両手を伸ばしコートの中から長い髪を出した。後ろに立っていたジャックに彼女の髪の香りがふわっと漂った。自然と伸びた手を止め、ジャックは慌てて軽く握りこぶしを作った。
(何、考えてんだ……?)
握りこぶしを見つめて居るところにくるりと振り返った彼女の頬は赤く火照っていて、酔っているのだと誰もが推測できるだろう。本当にこんな状態の彼女を一人で帰らせていいのだろうか、しかし一度断られた手前、又送ると言えばしつこいと思われてしまうのでは無いかと頭を悩ませていた。
どうするかはっきり決め兼ねていると彼女が別れの挨拶を始めてしまい、ジャックは結局言い出すことが出来ずに居た。
「あの、色々とありがとうございました。……じゃあ私はこれで」
深くお辞儀をするとすぐに背中を見せるのは気が引けるのか、ジャックに視線を向けながら駅へと向かう道を歩き出した。見るからに危なっかしい足元に、思わず手が伸びそうになる。
(危なっかしいなぁ。やっぱりしつこいって思われるのを覚悟でもう一回言おうか)
「あのっ……。――!」
側道に駐車していた車のドアが突然開いた事に後ろ向きで歩いている彼女は当然気付かずおぼつく足元で歩き続けた。
「――危ない!」
「え? ……きゃっ! ――。」
考えるのが早いか行動に移すのが早いか。気付けばジャックは彼女の腕を掴み、ぐっと自分の胸元に抱き寄せていた。彼女の体がフワッと彼の胸に吸い込まれ、居場所が判らない彼女の腕は頼りなくただぶら下がって居た。
車中から出てきた人物は彼がじっと睨み続けているのにも気付かず、足早にホテル内に消えていく。その事に思わず“チッ”と舌打ちをした。
ジャックが視線を戻して我に返ると、彼女が腕の中にいる事に気付き慌てて手を離す。
「ああ、っと、ごめん」
「い、いえ、私の方こそ! ボーっとしちゃって」
一歩下がり俯いている彼女は、先ほどより明らかに赤くなった顔をしていた。ポケットに手を突っ込んでいるジャックも又、照れくさそうに鼻を擦った。
「あの……、やっぱり危ないから送らせて?」
彼女は小さく頷いた。