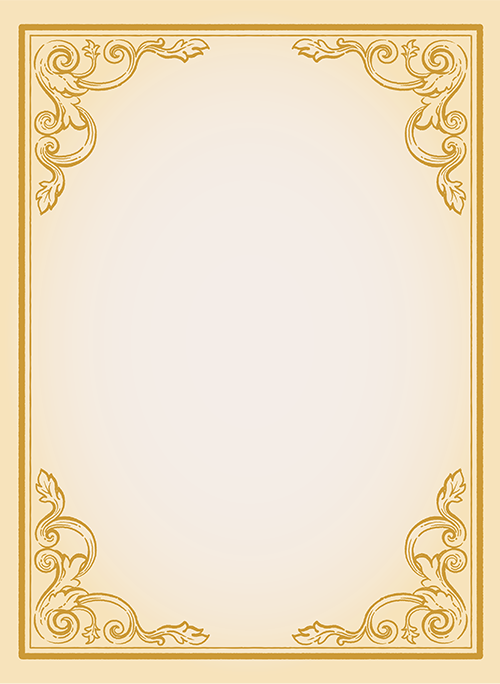初めて絵里香に彼を紹介したはずが、『初めまして』じゃなくて『ご無沙汰してます』と絵里香が言った。
ジャックも何処か記憶の端にあるのか、必死で思い出そうと絵里香を凝視している。
叶子は二人の接点が皆目検討もつかなくて、ただ二人の様子を黙って見ているだけだった。
「確か君は……」
「ラ・トゥールのパティシエールの佐々木です」
「ああ! そうだそうだ! お店で見るのとは服装が違うから判らなかったよ」
今の状況を説明して欲しそうに叶子が交互に二人を見ていると、それに気付いた絵里香がニコリと笑顔を浮かべた
「ジャックさんは良くうちに来てくださるのよ。ここ最近はとんと見かけなかったけど」
「あ? そうだったんだ」
「最近忙しくてね、久しくラ・トゥールには行けてないな。でもびっくりしたな君の友達だったなんて」
「ええ、私も目を疑いましたよ」
三人とも席に着くと、叶子は二人の話しの腰を折らないように小声で、『ペリエでいい?』とまだ仕事中の彼のためにソフトドリンクを勧める。『うん、お願い』と笑顔で返してくれた彼に嬉しくなりながら、店員を呼んで彼のドリンクをオーダーした。
「そうだ、門倉シェフは元気にしてるかい?」
二人はなんだか楽しそうにして、叶子には判らない話で盛り上がっている。そんな二人を横目で見つつ、少しつまはじきをくらった様な気持ちになり、ほんの少し口を尖らせていた。
「へー、そうか。じゃあ是非、又今度近いうちに寄らせてもらうよ。……? ――。」
そんな叶子の気持ちが判ったのか、絵里香と話を弾ませながらベンチシートに置いた叶子の手に、彼の大きくて暖かな手が上から重ねられる。
「――。……っ」
見えていないとはいえ、友達の前でのこの行為は少し気恥ずかしい。だが、それと同時に大きな安心感を与えられた気分になり、思わず顔が綻んだ。
「ああ、なるほど! それは凄い」
ジャックが絵里香に相槌を打ちながら、叶子の手の甲を彼の親指が何度も滑る。その優しい指使いに先程まで口を尖らせていたのが嘘の様に、表情が和らいでいった。
(ああ、この人には敵わないな)
ジャックの横顔を見上げそんな事を思いながら、二人の話しに耳を傾けていた。
「そうなんですよ、カナがラ・トゥールに居た頃は」
叶子がラ・トゥールで働いていたという事は当然ジャックも知っているかのように絵里香が話し出すと、ジャックは急に目を丸くして叶子の方へと振り向いた。大きな瞳を何度もパタつかせ、キョトンとしている。
「え? 君、あそこで働いてたの?」
「あ、うん。前言ってた学生時代のアルバイトでね。絵里香はその後もずっと続けて社員になったの」
「どうりで」
この間の旅を思い出したのか『料理が上手いはずだ』と叶子を見つめながら極上の甘顔で呟いた言葉は、絵里香にしたら惚気にしか聞こえないだろう。今のジャックの様子を見ていると、ここで『レシピが素晴らしいからだよ』何て言おうもんなら又意地悪な言葉を言われそうな気がする。親友の前という事もありそれを避けたかった叶子は、何も言わず頬を染めたまま小さく縮こまっていた。
「ジャックさんがうちに来られたのは確かカナが辞めてしばらくしてからだったけど、もしカナがまだ働いてたらどうなってたんでしょうね」
「ほんとに」
ジャックと叶子は目を合わせ、この巡り合わせに驚きの表情を隠せない様子だった。重ねられていた彼の手はしっかりと彼女の手を握り締め、それが『もう離さないよ』と言っている様にも見える。
「──あ」
ふと、彼が繋いだままの手を自分の目線まで持ち上げ、叶子の手首にある時計を見た。
「わ、もうこんな時間だ! ごめん、そろそろ戻らなきゃ」
ジャックが慌てて立ち上がり、絵里香にすっと手を伸ばす。
「会えて嬉しかったよ」
「こちらこそ。又お店でお待ちしております」
『今度は二人で来てくださいね』と絵里香が言いながら二人が握手を交わした後、叶子の方を向いて極々自然に頬に口づけた。
「又、電話するからね」
「う、うん」
ニッコリと微笑むと、そのまま出口へと進む。キャッシャーでこちらを指差しながら、上着の内ポケットに手を入れ従業員と何やら話していた。その様子と、普段の彼の行動からしてここの支払いをしてくれているのだなということが容易に判った。
しばらくして会計が済んだのかジャックは叶子に小さく手を振ると、ブラックコートの裾を翻して出口から姿を消した。
「──。」
「ご、ごめんね。何か慌しくって」
最後の最後にテーブルの下で手を繋いでいた事がバレた事に、叶子は動揺を隠し切れない。しかし、そんな事は絵里香はどうでも良かったのか、別段その事に触れる事も無かった。それどころかジャックが居なくなったのを確認した絵里香の口から、とんでもない言葉が飛び出した。
「あの人は……やめた方がいいよ」
先ほどまでとは全く違う顔つきで、絵里香がそう言った。
ジャックも何処か記憶の端にあるのか、必死で思い出そうと絵里香を凝視している。
叶子は二人の接点が皆目検討もつかなくて、ただ二人の様子を黙って見ているだけだった。
「確か君は……」
「ラ・トゥールのパティシエールの佐々木です」
「ああ! そうだそうだ! お店で見るのとは服装が違うから判らなかったよ」
今の状況を説明して欲しそうに叶子が交互に二人を見ていると、それに気付いた絵里香がニコリと笑顔を浮かべた
「ジャックさんは良くうちに来てくださるのよ。ここ最近はとんと見かけなかったけど」
「あ? そうだったんだ」
「最近忙しくてね、久しくラ・トゥールには行けてないな。でもびっくりしたな君の友達だったなんて」
「ええ、私も目を疑いましたよ」
三人とも席に着くと、叶子は二人の話しの腰を折らないように小声で、『ペリエでいい?』とまだ仕事中の彼のためにソフトドリンクを勧める。『うん、お願い』と笑顔で返してくれた彼に嬉しくなりながら、店員を呼んで彼のドリンクをオーダーした。
「そうだ、門倉シェフは元気にしてるかい?」
二人はなんだか楽しそうにして、叶子には判らない話で盛り上がっている。そんな二人を横目で見つつ、少しつまはじきをくらった様な気持ちになり、ほんの少し口を尖らせていた。
「へー、そうか。じゃあ是非、又今度近いうちに寄らせてもらうよ。……? ――。」
そんな叶子の気持ちが判ったのか、絵里香と話を弾ませながらベンチシートに置いた叶子の手に、彼の大きくて暖かな手が上から重ねられる。
「――。……っ」
見えていないとはいえ、友達の前でのこの行為は少し気恥ずかしい。だが、それと同時に大きな安心感を与えられた気分になり、思わず顔が綻んだ。
「ああ、なるほど! それは凄い」
ジャックが絵里香に相槌を打ちながら、叶子の手の甲を彼の親指が何度も滑る。その優しい指使いに先程まで口を尖らせていたのが嘘の様に、表情が和らいでいった。
(ああ、この人には敵わないな)
ジャックの横顔を見上げそんな事を思いながら、二人の話しに耳を傾けていた。
「そうなんですよ、カナがラ・トゥールに居た頃は」
叶子がラ・トゥールで働いていたという事は当然ジャックも知っているかのように絵里香が話し出すと、ジャックは急に目を丸くして叶子の方へと振り向いた。大きな瞳を何度もパタつかせ、キョトンとしている。
「え? 君、あそこで働いてたの?」
「あ、うん。前言ってた学生時代のアルバイトでね。絵里香はその後もずっと続けて社員になったの」
「どうりで」
この間の旅を思い出したのか『料理が上手いはずだ』と叶子を見つめながら極上の甘顔で呟いた言葉は、絵里香にしたら惚気にしか聞こえないだろう。今のジャックの様子を見ていると、ここで『レシピが素晴らしいからだよ』何て言おうもんなら又意地悪な言葉を言われそうな気がする。親友の前という事もありそれを避けたかった叶子は、何も言わず頬を染めたまま小さく縮こまっていた。
「ジャックさんがうちに来られたのは確かカナが辞めてしばらくしてからだったけど、もしカナがまだ働いてたらどうなってたんでしょうね」
「ほんとに」
ジャックと叶子は目を合わせ、この巡り合わせに驚きの表情を隠せない様子だった。重ねられていた彼の手はしっかりと彼女の手を握り締め、それが『もう離さないよ』と言っている様にも見える。
「──あ」
ふと、彼が繋いだままの手を自分の目線まで持ち上げ、叶子の手首にある時計を見た。
「わ、もうこんな時間だ! ごめん、そろそろ戻らなきゃ」
ジャックが慌てて立ち上がり、絵里香にすっと手を伸ばす。
「会えて嬉しかったよ」
「こちらこそ。又お店でお待ちしております」
『今度は二人で来てくださいね』と絵里香が言いながら二人が握手を交わした後、叶子の方を向いて極々自然に頬に口づけた。
「又、電話するからね」
「う、うん」
ニッコリと微笑むと、そのまま出口へと進む。キャッシャーでこちらを指差しながら、上着の内ポケットに手を入れ従業員と何やら話していた。その様子と、普段の彼の行動からしてここの支払いをしてくれているのだなということが容易に判った。
しばらくして会計が済んだのかジャックは叶子に小さく手を振ると、ブラックコートの裾を翻して出口から姿を消した。
「──。」
「ご、ごめんね。何か慌しくって」
最後の最後にテーブルの下で手を繋いでいた事がバレた事に、叶子は動揺を隠し切れない。しかし、そんな事は絵里香はどうでも良かったのか、別段その事に触れる事も無かった。それどころかジャックが居なくなったのを確認した絵里香の口から、とんでもない言葉が飛び出した。
「あの人は……やめた方がいいよ」
先ほどまでとは全く違う顔つきで、絵里香がそう言った。