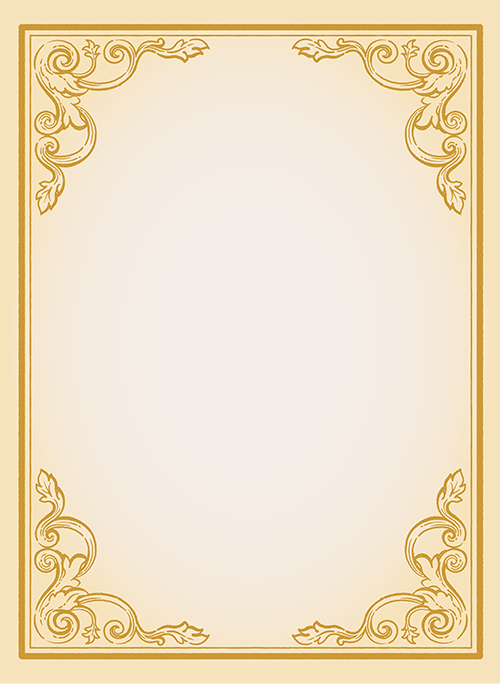寒かった心も、温かい風が吹き込んできたような感覚が私を包み込む。
――初めて会う人に、こんなに簡単に心を許していいのだろうか?
頭の片隅にあった彼女の警戒心はいつの間にか消え去っていたことに自分自身が一番驚いていた。
『食事でも』と言われ、思わず両手を天に振りかざしたい位に気持ちが昇りつめたが、そこをグッと我慢してゆっくりと顔を上げ嬉しそうに口をすぼめてコクンと小さく頷いた。
「良かった。……じゃあ、行こうか」
「はい!」
そう言うや否や、彼は長い足をフルに活用してスタスタとロビーを歩き出した。慌てて駆け出し叶子は彼の数歩後ろをついて歩いた。
改めて見る彼の後姿に以前見た雨の中を傘もささず走りだした背中と重ねる。華奢だと思っていた彼は、明るいところでよく見ると結構がっしりしているように見えた。そして歩くたびに弾む彼の柔らかそうな黒髪は、つい手が伸びてしまいそうなほど綺麗に手入れがされているようだった。
そしてこの彼の甘い香りが鼻孔をくすぐり、こうやって彼の後ろを歩くだけで彼の香りに包まれた気分になっていた。
(いい香り……なんの香りだろう)
ほんの少し目を細めながら彼の香りの元となる成分を分析していると、突然立ち止まった彼の背中にボスッと顔を埋めてしまった。
「きゃっ! ごめんなさい」
彼は背中に埋もれた彼女をチラっと見て少し微笑んだ後、彼が急に立ち止まった原因となる方向に向きなおした。
「こんばんは。今日はどうされたんですか?」
「やあ、こんばんは。今日はそこのディナーを予約したんだ」
ロビーの隅にある落ち着いた照明のレストランの入り口らしき場所を親指で指し示した。
「そうですか。今度うちにもいらして下さいね」
「ああ、じゃあ来週伺おうかな。又秘書から連絡入れます」
「ありがとうございます。では来週お待ちしております」
髪をきっちりと整え、皺一つない黒服に身を包んだホテルマンが深々と頭を下げると、彼は片手を上げて又歩き始めた。
この一連のやり取りで彼がここの常連だという事がよく判る。もしかすると相当なお金持ちなのかも知れないと言う事に今更ながら気が付いた。初めて会った見ず知らずの人間にこれはプレゼントだとCDを渡された時、この人はただものではないなとは思ってはいたものの、貰った名刺には役職を表すようなものは一切書いておらず、正直、今日会ってみるまで本当は実在しない人物なのでは無いかと疑心暗鬼になっていた。
(凄いなぁ。会社からこんなに近いけど、私はトイレしか利用した事ないのに)
感心しながらも足を進めると、先程のレストランの入り口に立っているスタッフが彼を見つけ、すぐさま声を掛けてきた。
「こんばんは。お待ちしておりました」
「やあ、こんばんは」
「どうぞこちらへ」
(うっわぁ……。又もや顔パス? 名前も何も言ってないのにあっさり入れるなんて、経験した事ないよ。しかもこんな超高級ホテルで)
ちょっとした感動を味わいながらも案内されて店内に入ると、更に叶子を感動させるモノが視界に入った。
白亜の壁一面に飾られている大きな絵。
思わずそれに見とれてしまった叶子の歩く歩幅が徐々に狭くなっていった。、
「この絵 凄くいいよね」
「……ええ、何と言うか。本当、凄い……って、ごめんなさい。大した感想も言えなくて」
「いやいや、君のその感激した様子を見ていると、本当にこの絵は凄いんだなって良く判るよ」
彼は何だか嬉しそうにしている。まるで自分が書いた絵を褒められたかのような言いっぷりに叶子も口角がキュッと上がった。
絵を眺めながら再度足を進めだすと、前方を歩いていた彼が又ピタッと足を止める。すぐに気配を察知した彼女は今度は彼にぶつからずに立ち止まり、ホッと胸を撫で下ろした。
ギリギリの所でぶつかってしまうのを回避できた彼女を見て、彼はニッコリと微笑んでいた。
「そっち?」
「あ、はい。いつもの様に個室をお取りしておりますが?」
「あー、今日はプライベートで来てるからこっちでいいよ。こっちの方が景色が楽しめるからね」
「あ、はい、かしこまりました。お席は禁煙席でとの事ですが、宜しいでしょうか」
「うん。……あーっと、君、煙草吸わないよね?」
「あ、はい」
(なんで煙草吸わないって決め付けられるんだろう? そんな話、電話でしたかなぁ?)
そんなやり取りをした覚えがなく、叶子は丸くて大きな目をきょとんとさせた。
「僕ね、凄く耳がいいんだ」
「耳――ですか?」
「うん、その人の声の質で喫煙者かどうか聞き分けられるんだよ」
「へぇ! 凄いですね」
『僕の特技なんだ』そう言って、どこか誇らしげに彼は胸を張っていた。
案内された席は彼の言ったとおり、それはそれは目を見張るものであった。硝子張りの向こうは綺麗に手入れをされた庭園が広がっていて、無数のイルミネーションが施されている。この景色を見るだけでも価値がある。そう言ってもおかしくないほど、目の前の景色は叶子の目を楽しませてくれた。
斜めにセッティングされたテーブルの一辺で椅子を引かれた。庭園を見るようにして座る彼女の横に彼も同じく椅子を引かれて座る。まるで恋人同士のようにして並んで座る事に驚きながらも、決してそれが嫌というわけでもなかった。
彼女の口元が意思とは反して勝手に緩んでいく。そんな風に思われているとは知らず、彼はなおも彼女に顔を近づけた。
「もう少しあったかくなるとね、ここにリスが来るんだよ」
そう言うと、彼女に見えやすいように硝子の向こうを指差した。予想外に接近され彼の顔をまともに見る事が出来ない。叶子は彼の指差す方に目を凝らし、必死に平常心を装った。
「……へ、へー。こんな都会にリスが来るんですか?」
「そう。ここで飼ってるらしいんだけど、たまに逃げ出すんだって」
――だろ?
椅子を引いてくれたスタッフに嬉しそうに問いかけた。
ニコニコとあどけない表情を見せる彼。夢で見た彼とは全く違い、想像通りの心の穏やかな人だと感じた。
「――あ、何がいい? 嫌いなものある?」
「――。あ、えっと、そうですねぇ……」
彼は明らかに今まで出会ってきた男性と違う。彼の事をもっと知りたい。ただ、漠然とそう思うのだった。
――初めて会う人に、こんなに簡単に心を許していいのだろうか?
頭の片隅にあった彼女の警戒心はいつの間にか消え去っていたことに自分自身が一番驚いていた。
『食事でも』と言われ、思わず両手を天に振りかざしたい位に気持ちが昇りつめたが、そこをグッと我慢してゆっくりと顔を上げ嬉しそうに口をすぼめてコクンと小さく頷いた。
「良かった。……じゃあ、行こうか」
「はい!」
そう言うや否や、彼は長い足をフルに活用してスタスタとロビーを歩き出した。慌てて駆け出し叶子は彼の数歩後ろをついて歩いた。
改めて見る彼の後姿に以前見た雨の中を傘もささず走りだした背中と重ねる。華奢だと思っていた彼は、明るいところでよく見ると結構がっしりしているように見えた。そして歩くたびに弾む彼の柔らかそうな黒髪は、つい手が伸びてしまいそうなほど綺麗に手入れがされているようだった。
そしてこの彼の甘い香りが鼻孔をくすぐり、こうやって彼の後ろを歩くだけで彼の香りに包まれた気分になっていた。
(いい香り……なんの香りだろう)
ほんの少し目を細めながら彼の香りの元となる成分を分析していると、突然立ち止まった彼の背中にボスッと顔を埋めてしまった。
「きゃっ! ごめんなさい」
彼は背中に埋もれた彼女をチラっと見て少し微笑んだ後、彼が急に立ち止まった原因となる方向に向きなおした。
「こんばんは。今日はどうされたんですか?」
「やあ、こんばんは。今日はそこのディナーを予約したんだ」
ロビーの隅にある落ち着いた照明のレストランの入り口らしき場所を親指で指し示した。
「そうですか。今度うちにもいらして下さいね」
「ああ、じゃあ来週伺おうかな。又秘書から連絡入れます」
「ありがとうございます。では来週お待ちしております」
髪をきっちりと整え、皺一つない黒服に身を包んだホテルマンが深々と頭を下げると、彼は片手を上げて又歩き始めた。
この一連のやり取りで彼がここの常連だという事がよく判る。もしかすると相当なお金持ちなのかも知れないと言う事に今更ながら気が付いた。初めて会った見ず知らずの人間にこれはプレゼントだとCDを渡された時、この人はただものではないなとは思ってはいたものの、貰った名刺には役職を表すようなものは一切書いておらず、正直、今日会ってみるまで本当は実在しない人物なのでは無いかと疑心暗鬼になっていた。
(凄いなぁ。会社からこんなに近いけど、私はトイレしか利用した事ないのに)
感心しながらも足を進めると、先程のレストランの入り口に立っているスタッフが彼を見つけ、すぐさま声を掛けてきた。
「こんばんは。お待ちしておりました」
「やあ、こんばんは」
「どうぞこちらへ」
(うっわぁ……。又もや顔パス? 名前も何も言ってないのにあっさり入れるなんて、経験した事ないよ。しかもこんな超高級ホテルで)
ちょっとした感動を味わいながらも案内されて店内に入ると、更に叶子を感動させるモノが視界に入った。
白亜の壁一面に飾られている大きな絵。
思わずそれに見とれてしまった叶子の歩く歩幅が徐々に狭くなっていった。、
「この絵 凄くいいよね」
「……ええ、何と言うか。本当、凄い……って、ごめんなさい。大した感想も言えなくて」
「いやいや、君のその感激した様子を見ていると、本当にこの絵は凄いんだなって良く判るよ」
彼は何だか嬉しそうにしている。まるで自分が書いた絵を褒められたかのような言いっぷりに叶子も口角がキュッと上がった。
絵を眺めながら再度足を進めだすと、前方を歩いていた彼が又ピタッと足を止める。すぐに気配を察知した彼女は今度は彼にぶつからずに立ち止まり、ホッと胸を撫で下ろした。
ギリギリの所でぶつかってしまうのを回避できた彼女を見て、彼はニッコリと微笑んでいた。
「そっち?」
「あ、はい。いつもの様に個室をお取りしておりますが?」
「あー、今日はプライベートで来てるからこっちでいいよ。こっちの方が景色が楽しめるからね」
「あ、はい、かしこまりました。お席は禁煙席でとの事ですが、宜しいでしょうか」
「うん。……あーっと、君、煙草吸わないよね?」
「あ、はい」
(なんで煙草吸わないって決め付けられるんだろう? そんな話、電話でしたかなぁ?)
そんなやり取りをした覚えがなく、叶子は丸くて大きな目をきょとんとさせた。
「僕ね、凄く耳がいいんだ」
「耳――ですか?」
「うん、その人の声の質で喫煙者かどうか聞き分けられるんだよ」
「へぇ! 凄いですね」
『僕の特技なんだ』そう言って、どこか誇らしげに彼は胸を張っていた。
案内された席は彼の言ったとおり、それはそれは目を見張るものであった。硝子張りの向こうは綺麗に手入れをされた庭園が広がっていて、無数のイルミネーションが施されている。この景色を見るだけでも価値がある。そう言ってもおかしくないほど、目の前の景色は叶子の目を楽しませてくれた。
斜めにセッティングされたテーブルの一辺で椅子を引かれた。庭園を見るようにして座る彼女の横に彼も同じく椅子を引かれて座る。まるで恋人同士のようにして並んで座る事に驚きながらも、決してそれが嫌というわけでもなかった。
彼女の口元が意思とは反して勝手に緩んでいく。そんな風に思われているとは知らず、彼はなおも彼女に顔を近づけた。
「もう少しあったかくなるとね、ここにリスが来るんだよ」
そう言うと、彼女に見えやすいように硝子の向こうを指差した。予想外に接近され彼の顔をまともに見る事が出来ない。叶子は彼の指差す方に目を凝らし、必死に平常心を装った。
「……へ、へー。こんな都会にリスが来るんですか?」
「そう。ここで飼ってるらしいんだけど、たまに逃げ出すんだって」
――だろ?
椅子を引いてくれたスタッフに嬉しそうに問いかけた。
ニコニコとあどけない表情を見せる彼。夢で見た彼とは全く違い、想像通りの心の穏やかな人だと感じた。
「――あ、何がいい? 嫌いなものある?」
「――。あ、えっと、そうですねぇ……」
彼は明らかに今まで出会ってきた男性と違う。彼の事をもっと知りたい。ただ、漠然とそう思うのだった。