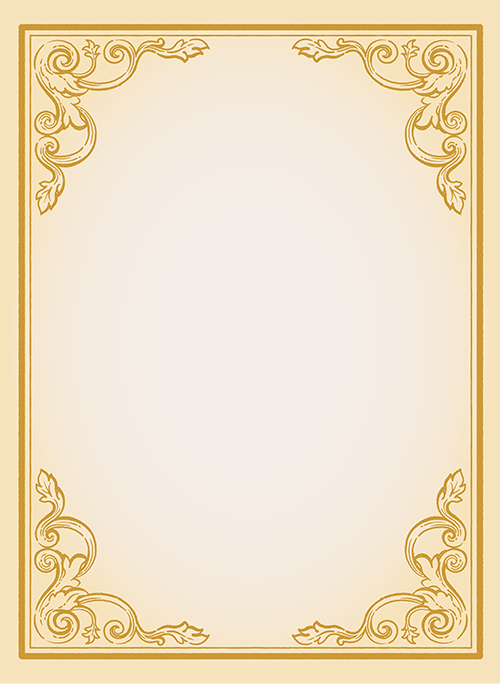「ねぇ。この間あんたが言ってた、新しく出来たあの店。今日この後行って見ない?」
そう言いながら叶子のデスクに両手をつき、同期の藍子が彼女宛の荷物をわざわざ届けてくれた。
あの店の話をした時は一切関心を示さなかったのに、いつもと何処か違う彼女の様子を察したのか急に誘いをかけてきたのだった。
恐らく彼女がしきりに時計を気にしたり、いつもと出で立ちが違うのが気にかかったのだろう。同期と言えども、入社してからやたらと対抗意識を勝手に燃やしていた藍子のことだ、きっと妨害したくてたまらないのだと彼女は既に感づいていた。
「あー、ごめん。今日は用事があるから、又今度ね」
キーボードを弾く手を止めず、チラリと横目で見ながら藍子に微笑む彼女の態度がどこか余裕を感じさせられる。藍子はそれも気に食わないのか、まだ何か言いたげな表情で叶子を見つめていた。
「ふぅん。――何処行くの?」
「あー、ちょっとごめん……あ、もしもし?」
そう聞かれると思い、藍子が言うよりも先に受話器を取り取引先へとダイアルしながらなんなくやり過ごすと、明らかにむすっとした表情を浮かべながら藍子は諦めて自席へと戻っていった。
あと少しで彼に会えると思うと電話の声がいつもより自然に1トーン高くなり、いつもは人前で鼻歌なんて歌わない彼女が電話の保留音に合わせ、弾けもしないピアノを弾いている振りをしながら自然と鼻歌を歌っていた。
気がつけば窓の外はすっかり暗くなっていて既に約束の時間が迫っている。
藍子に見つかったら又しつこく尋問されると思った彼女は、気持ち頭を低くしながらオフィスを後にした。
都会の冬の夜はとても寒い。ビル風が容赦なく彼女を吹きさらし、あっという間に体温を奪い去って行く。吐き出す息は白く、手袋をしている指先も氷の様に冷たくなるのに、そう時間は掛からなかった。
(あの日もこんな感じだったなぁ)
そろそろ彼の事を思い出してもいいだろうかと、自分の抑えつけていたものを解き放つかのようにあの日初めて出会った時の事、電話で話した事を思い返しては顔をほころばせていた。
あの角を曲がれば約束の場所。
近づくにつれ彼女の鼓動も速度を増す。
(彼が来たらなんて言おう? 『一緒に食事でも……』とか誘ってもらえるのかな? 『わざわざありがとう、じゃあ』とかだけだったら……、寂しいかも)
叶子が笑ったり落ち込んだりしながら歩いている様は、傍(はた)から見るとなんだか楽しそうに見えているだろう。すれ違う人の視線を感じ、慌てて口元を正した。
◇◆◇
コツン、コツンとピンヒールの音が静かなロビーに響く中、彼女は辺りをキョロキョロと見回しながら彼らしき人物を探している。
(まだ……来てない、――かな?)
コートの袖をめくり、時計の針を確認した。
「――あの!」
あの時の甘い香りが辺りに広がる。慌てて振り返ると、そこには息を切らした彼が立っていた。あの時と同じ優しそうな彼の瞳を見つけ、彼女の鼓動が更に激しく鳴り始める。
「あぁ、良かった、間に合った!」
彼は大きな手の平を胸に当て、自分を落ち着かせるようにふーっと息を吐いた。
「あ、あの、そ、その……」
さっきまで会った時に何を話そうかと散々悩み考えていたと言うのに、いざとなると思うように言葉が出てきてくれない。『あの、その』を繰り返し混乱する彼女の表情を見て、彼はニッコリと微笑んだ。
「こんばんは」
そう言って彼が右手を差し出し、動揺していた叶子も合わせて右手を差し出した。
「あ、こ、こんばんは」
濁りの無い澄んだ瞳に吸い込まれそうな錯覚に陥りながらも、彼女は努めて冷静に振舞おうとした。しかし指先が彼の手に触れた途端、驚いた表情を見せた彼にそのまま両手で包みこまれてしまい、落ち着きを取り戻す事は出来なかった。
「えっ!? まさかこの寒い中歩いてきたの? 手が凄く冷たくなっているよ?」
手を握られた。たったそれだけの事だが、叶子の胸の音を更に早めるには十分過ぎる出来事だった。まだ良く知りもしない見ず知らずの男性に手を握り締められる事はまずないし、こんなに温かく柔らかい男性の手も触れた事も無い。一気に頬に熱を帯びだしたのが判るとますます胸の鼓動が加速を始める。
「ちっ! 近いので!」
そう言うだけで精一杯だった。握られた手を払い除ける事も出来ず、叶子は紅潮した頬を見られないようにと下を向いて自分の足元を見ている。その仕草を見て察したのかジャックは慌てて手を離すと彼も又気恥ずかしいのだろう、片方の手をポケットに突っ込み、もう一方の手は手持ち無沙汰に自分の唇を触っていた。
「あの、電話で言うの忘れてたんだけど……。良かったら今から一緒に食事でも」
「……。」
その台詞を聞いた途端、うつむいていた彼女の顔は見る見る笑顔に変わり、この後に続くかもしれない未来に少しばかり期待を寄せた。
そう言いながら叶子のデスクに両手をつき、同期の藍子が彼女宛の荷物をわざわざ届けてくれた。
あの店の話をした時は一切関心を示さなかったのに、いつもと何処か違う彼女の様子を察したのか急に誘いをかけてきたのだった。
恐らく彼女がしきりに時計を気にしたり、いつもと出で立ちが違うのが気にかかったのだろう。同期と言えども、入社してからやたらと対抗意識を勝手に燃やしていた藍子のことだ、きっと妨害したくてたまらないのだと彼女は既に感づいていた。
「あー、ごめん。今日は用事があるから、又今度ね」
キーボードを弾く手を止めず、チラリと横目で見ながら藍子に微笑む彼女の態度がどこか余裕を感じさせられる。藍子はそれも気に食わないのか、まだ何か言いたげな表情で叶子を見つめていた。
「ふぅん。――何処行くの?」
「あー、ちょっとごめん……あ、もしもし?」
そう聞かれると思い、藍子が言うよりも先に受話器を取り取引先へとダイアルしながらなんなくやり過ごすと、明らかにむすっとした表情を浮かべながら藍子は諦めて自席へと戻っていった。
あと少しで彼に会えると思うと電話の声がいつもより自然に1トーン高くなり、いつもは人前で鼻歌なんて歌わない彼女が電話の保留音に合わせ、弾けもしないピアノを弾いている振りをしながら自然と鼻歌を歌っていた。
気がつけば窓の外はすっかり暗くなっていて既に約束の時間が迫っている。
藍子に見つかったら又しつこく尋問されると思った彼女は、気持ち頭を低くしながらオフィスを後にした。
都会の冬の夜はとても寒い。ビル風が容赦なく彼女を吹きさらし、あっという間に体温を奪い去って行く。吐き出す息は白く、手袋をしている指先も氷の様に冷たくなるのに、そう時間は掛からなかった。
(あの日もこんな感じだったなぁ)
そろそろ彼の事を思い出してもいいだろうかと、自分の抑えつけていたものを解き放つかのようにあの日初めて出会った時の事、電話で話した事を思い返しては顔をほころばせていた。
あの角を曲がれば約束の場所。
近づくにつれ彼女の鼓動も速度を増す。
(彼が来たらなんて言おう? 『一緒に食事でも……』とか誘ってもらえるのかな? 『わざわざありがとう、じゃあ』とかだけだったら……、寂しいかも)
叶子が笑ったり落ち込んだりしながら歩いている様は、傍(はた)から見るとなんだか楽しそうに見えているだろう。すれ違う人の視線を感じ、慌てて口元を正した。
◇◆◇
コツン、コツンとピンヒールの音が静かなロビーに響く中、彼女は辺りをキョロキョロと見回しながら彼らしき人物を探している。
(まだ……来てない、――かな?)
コートの袖をめくり、時計の針を確認した。
「――あの!」
あの時の甘い香りが辺りに広がる。慌てて振り返ると、そこには息を切らした彼が立っていた。あの時と同じ優しそうな彼の瞳を見つけ、彼女の鼓動が更に激しく鳴り始める。
「あぁ、良かった、間に合った!」
彼は大きな手の平を胸に当て、自分を落ち着かせるようにふーっと息を吐いた。
「あ、あの、そ、その……」
さっきまで会った時に何を話そうかと散々悩み考えていたと言うのに、いざとなると思うように言葉が出てきてくれない。『あの、その』を繰り返し混乱する彼女の表情を見て、彼はニッコリと微笑んだ。
「こんばんは」
そう言って彼が右手を差し出し、動揺していた叶子も合わせて右手を差し出した。
「あ、こ、こんばんは」
濁りの無い澄んだ瞳に吸い込まれそうな錯覚に陥りながらも、彼女は努めて冷静に振舞おうとした。しかし指先が彼の手に触れた途端、驚いた表情を見せた彼にそのまま両手で包みこまれてしまい、落ち着きを取り戻す事は出来なかった。
「えっ!? まさかこの寒い中歩いてきたの? 手が凄く冷たくなっているよ?」
手を握られた。たったそれだけの事だが、叶子の胸の音を更に早めるには十分過ぎる出来事だった。まだ良く知りもしない見ず知らずの男性に手を握り締められる事はまずないし、こんなに温かく柔らかい男性の手も触れた事も無い。一気に頬に熱を帯びだしたのが判るとますます胸の鼓動が加速を始める。
「ちっ! 近いので!」
そう言うだけで精一杯だった。握られた手を払い除ける事も出来ず、叶子は紅潮した頬を見られないようにと下を向いて自分の足元を見ている。その仕草を見て察したのかジャックは慌てて手を離すと彼も又気恥ずかしいのだろう、片方の手をポケットに突っ込み、もう一方の手は手持ち無沙汰に自分の唇を触っていた。
「あの、電話で言うの忘れてたんだけど……。良かったら今から一緒に食事でも」
「……。」
その台詞を聞いた途端、うつむいていた彼女の顔は見る見る笑顔に変わり、この後に続くかもしれない未来に少しばかり期待を寄せた。